「冠婚葬祭 > 香典袋」の商品をご紹介します。

のし 熨斗 熨斗袋 不祝儀 袋 香奠 お香典 ご香典 香典 香典袋 キリスト教 カトリック 追悼ミサ 命日祭 万霊祭 お彼岸 仏教 お悔み お悔やみ 封筒 冠婚葬祭特選多当のし袋 御霊前 御佛前 御布施 御花料 1枚入 | ササガワ のし 熨斗 熨斗袋 不祝儀 袋 香奠 お香典 ご香典 香典 香典袋 お通夜 通夜 葬式 葬儀 お葬式 御仏前 お仏前 御佛前 お布施 お霊前 御霊前 慶弔用品 慶弔袋 仏事 金封
【入り数】1枚 【サイズ】本体-縦180mm×横95mm、中袋(封筒)-縦173mm×横85mm 【材質】上質紙(128g/m2) 多当のし袋の基本知識 多当のし袋とは多当のし袋の「多当」は「畳=たとう」が語源と言われています。鎌倉から室町時代のころより上流階級の人たちの間で使われていた懐紙(「ふところがみ」または「かいし」)や、茶の湯の菓子などを飲食する際に使われていた畳紙(「たとうし」)など、「携帯するのに便利なように折り畳んでいた」ことから名がつけられ、そこから経緯を経て「多当」となったとされています。また、金封の本体紙の折り方は、東日本では多当折りという四方折り方式で、西日本では風呂敷折りという斜め折り方式になっています。多当折りに限り裏折り返しの合わせ部分で祝い用と弔い用に区別しており、弔い用は「頭を垂れて悲しみを表す」として上部からの折り返しを上にすることになっています。サイズは180mm×95mmです。表書きがプリントされているので、名前を書き入れるだけでご使用いただけ、通夜・葬儀告別式時の際に、喪家に対して贈る弔慰金に最適です。 タイプ品番 御霊前6-5090 御佛前6-5091 御布施6-5092 御花料6-5095 【同一商品ゆうパケット同梱可能数】 9点までゆうパケット対応タイプ品番 御霊前6-5090 御佛前6-5091 御布施6-5092 御花料6-5095 多当のし袋のマナー 蓮が入ったものは、仏教の通夜・葬儀告別式時の際に、喪家に対して贈る弔慰金に用いられるものです。蓮の絵のないものは、仏教・神道・キリスト教など各宗教共通に通夜・葬儀告別式・法要時の際に、喪家に対して贈る弔慰金に用いられます。なお、仏教の通夜・葬儀告別式時に「蓮絵入」を用いても、法要時に「蓮絵入」では喪の意味合いが強過ぎるとの理由で、「蓮絵なし」や「黄水引」を用いる場合があります。いざというときに必要な仏用ののし袋は常用品としてもおすすめです。のし袋にお札を入れる際、お札の方向に特別な決まりはありませんが、中袋を表から見てお札の人物の顔が上になる様に入れると良いとされています。 のし袋の表側には、贈り手の気持を表すために表書きを施します。表書きには「御香料」「御香奠」などの文字を書き、贈り手の名前ものし袋に書く必要がありますが、こちらは「御霊前」のプリントがされているので表書きよりも少し小さめに名前を記載することを心掛けましょう。中袋の表側には包んだ金額を記載し、中袋の裏側には贈り手の名前と住所を書きます。 多当のし袋の使い方 表書き(献辞)に使用する「御霊前」は亡くなった方の御霊(みたま)の前にという意味合いがあり、「御佛前」は亡くなった方が成仏(じょうぶつ)した仏様の前にという意味合いがあります。仏教界では亡くなって御霊となった故人は忌明けをもって成仏するとの教えから、通夜、葬儀・告別式から忌明け直前までの法要には「御霊前」を、忌明け法要以降の全ての法要には「御佛前」を用いることになっています。但し、浄土真宗に限り、死とともに仏となって浄土に生まれ変わるとの教えから、通夜、葬儀・告別式から「御佛前」を用いることになっています。 尚、仏式ではあるが宗旨が不明という場合は「御香奠」として持参するのが無難です。神道では、故人は御霊となり、霊璽[れいじ]に移って後は神となるとの教えから、弔い事の儀式全般に「御霊前」や「御神前」を用いることが出来ます。キリスト教では、故人は霊魂となって神に召されるとの教えから、「御霊前」は弔い事の儀式全般に用いることが出来ます。「御布施」の記載がされたのし袋は弔事(お葬式や法事)の際に、寺院・僧侶への謝礼を渡す場合での使用がおすすめです。本来の意味は「他人に金品を施すこと」を言いますが、仏教におけるお布施はご本尊に「感謝の気持ちで施し供える」との意味合いがあります。形の上では、葬儀や法要において回向や供養を頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いるものですが、本来はご本尊への施しお供えであることから、受取るお寺側の方では「お預かりする」という受取り方をします。「御花料」の記載がされたのし袋はキリスト教(カトリック)の三十日目の追悼ミサ時にお供え金を贈る場合での使用がおすすめです。「御花料」を御花代と同意語だと考えて、お供えするお花の代金と間違って捉えられることがありますが、「料」とは「○○に替えて」という意味を持つもので、葬儀や法要で用いる弔慰金の「御花料」は「お花に替えてお供えします」という意味合いがあります。
198 円 (税込 / 送料別)

100万円まで入る婚礼用金封 100万円まで入る仏事用金封 婚礼 結婚式 お祝い 仏事 ご祝儀 不祝儀 100万円用 祝儀 袋 100万円 金封100万円まで入る金封 特大判 ササガワ | 100万円まで入る婚礼用金封 100万円まで入る仏事用金封 婚礼 結婚式 お祝い 仏事 ご祝儀 不祝儀 100万円用 祝儀 袋 100万円 金封
【入り数】3枚袋入 【サイズ】本体-縦220mm×横145mm、中袋(大阪折)-縦195mm×横124mm、OA短冊紙厚-0.095mm(仏事用のみ) 【材質】和紙 金封(祝用)の基本知識 金封(祝用)とは婚礼用のご祝儀袋(金封)です。紙幣一万円札で100万円まで入ります。光沢感のある紙が繊細に輝きます。シンプルな梅結びでモダンさも演出し、豪華で上品な最高の逸品となっております。包む金額の目安は30~100万円です。短冊(金寿/御結婚御祝/無字)、中袋付き。 金封(仏用)の基本知識 金封(仏用)とは仏事用の金封です。紙幣一万円札で100万円まで入ります。双銀あわじ変形の水引と、凹凸のある紙質は、厳かで上品な印象を与えます。手書き専用の短冊とは別に、プリンター対応短冊がセットになっているので無料テンプレートを使用し簡単に印刷して制作できます。葬儀や法事に最適です。包む金額の目安は30~100万円です。短冊(御霊前/御佛前/御香奠)、中袋付き。 タイプ品番 婚礼用27-5960 仏事用27-5961金封(祝用)について 金封(祝用)の折り重ね方金封には祝い折りと弔い折りがあって、現在のものはいずれも祝い折りの形が残っています。多当折りの金封やのし袋の内、上下の折り込みが裏面で交わる形式のものは、慶弔によって重ねあわせる方向が異なりますので注意が必要です。祝い事に用いるものは、「天を仰いで喜びを表す」との意から、裏面下部の折り返しの方を上になるように折り重ねて用います。金封(祝用)の表書きのマナー表側には、贈り手の気持を表すために表書きを施します。こちらの金封には短冊が付属していますので、そちらに表書きと、送り主の名前を書く必要があります。「寿」・「御結婚御祝」の短冊を使用する際には文字が印刷されているので、名前を書き入れるだけですぐにお使い頂けます。名前を入れる際は、個人名のみの場合は名前を上部より小さめに書き入れてください。表書きと送り主を記載する場合は黒色で文字を記します。赤や青など他の色を使うことはありませんので注意してください。また、中袋にも文字を記載する必要があります。中袋表面には金額を、中袋裏面には名前・住所を記入します。旧漢字を用いるのが正式ですが、略式(一、二、三)を使い、最後の「也」も省略してもかまいません。金封(祝用)のお札のマナー金封の中袋やのし袋にお札を入れる際、お札の方向に特別な決まりはありませんが、中袋を表から見てお札の人物の顔が上になる様に入れると良いとされています。婚礼においては、折る・汚れるなどを忌み嫌うことから、封入する紙幣は出来るだけ折り目や汚れのない新札を使用します。また封入紙幣の枚数(金額)は幸運の数字と言われる3枚・5枚・8枚が良いとされ、「祝御結婚」などの献辞(表書き)の字数ともども、4や9の付くものは死(四)や苦(九)に、6は「ろくでなし」に通じると、忌み嫌われることからなるべく避けた方が賢明です。「祝御結婚」は「御結婚御祝」と5文字にするとよいでしょう。元々は中国の古い学説で、「奇数は陽の数字、偶数は陰の数字」という陰陽説からきており、陰に当たる偶数は縁起が悪く、陽に当たる奇数は縁起が良い数字とされることからきているようです。一方では、奇数や偶数に関係なく、「4・6・9」のような言い回し方を始め、「1」は全ての事の始まり、「2」は双方が交わる、「8」は末広がり、「10」は満ち足りて事が成就したなどと言って、それぞれを吉とする日本古来の考え方も影響して、「1・2・3・5・7・8・10」は吉兆の数字で良いとされることから、封入する紙幣の枚数や祝儀袋の表書き(献辞=上書き)の字数に用いられています。金封は包む金額に合わせて大きさを選び、金封が大きく、水引の本数が多く色が豪華なほど高額のお包み用となります。こちらの金封の包む金額の目安は1~5万円以上です。 金封(仏用)について 金封(仏用)の折り重ね方弔い事に用いるものは、「頭(こうべ)を垂れて悲しみを表す」との意から裏面上部の折り返しの方を上になるように折り重ねて用います。金封(仏用)の表書きのマナー表側には、贈り手の気持を表すために表書きを施します。「御霊前」、「御佛前」、「御香奠」の短冊を使用する際には文字が印刷されているので、名前を書き入れるだけですぐにお使い頂けます。名前を入れる際は、個人名のみの場合は名前を上部より小さめに書き入れてください。表書きと送り主を記載する場合は黒色で文字を記します。赤や青など他の色を使うことはありませんので注意してください。また、中袋にも文字を記載する必要があります。中袋表面には金額を、中袋裏面には名前・住所を記入します。旧漢字を用いるのが正式ですが、略式(一、二、三)を使い、最後の「也」も省略してもかまいません。 タイプ品番 婚礼用27-5960 仏事用27-5961 金封(祝用)を使用する場面 冠婚葬祭儀式の「婚」にあたる婚礼は、古来より「葬」にあたる弔い行事とともに礼節が重んじられ、婚約・結納の儀から結婚の儀までの一連の儀式が厳粛に行われてきました。結婚式や披露宴の形式が時代と共に変化していってもなお、基本となる結婚のしきたりは脈々と継承されています。祝い金の元々は、結婚披露の宴会に招かれた出席者が各々に宴会用の酒や肴を持参して集まり祝った事の名残で、婚儀にまつわる一連の費用を部分負担してあげるという相互扶助の意味合いがあります。結婚祝いを贈る際、 正式には、結婚式の1ヵ月前~1週間前くらいまでの相手の都合のよい吉日を選んで本人宅に訪問持参するのが基本のマナーです。手渡す時はお盆に祝い金(袋)をのせ、袱紗をかけて渡します。挙式当日に持参する場合は受付で袱紗から取り出して「本日は誠におめでとうございます」などと挨拶した後に、金封の下方を相手に向けて差し出します。祝用の金封は結婚祝いに用いられることが多いですが、その華やかな見た目と格式のある水引の仕様から、さまざまな慶事の場面で幅広く活用されています。たとえば、職場の同僚や部下が結婚する際、上司や同僚一同からまとめて贈る際にも適しており、表書きを連名にすることで、複数人での祝意を一つに込めて贈ることができます。また、親戚や友人が婚約した際の婚約祝いとしても使用されることがあり、正式な結納ではないが感謝や祝福の気持ちを形にしたい場合にふさわしい封筒です。さらに、結婚記念日や銀婚式、金婚式などの節目を迎えるご夫婦に対して、家族や友人、親族から感謝の気持ちや長年の歩みへの敬意を込めたお祝い金を包む場面でも、祝用の金封は用いられます。水引の華やかさや短冊の使い分けが可能な点が、こうした多様な祝い事に対応しやすい要因となっています。特に「寿」や「御祝」といった表書きは、結婚に限らず、人生の門出や記念にまつわるあらゆる祝事に対応可能で、用途に応じて使い分けることで、より丁寧で心のこもった印象を与えることができます。そのほか、結婚式に出席しない場合でも、新郎新婦へのお祝いとして祝用の金封を用いて郵送または手渡しで贈るケースもあります。遠方に住む親族や友人が「御結婚御祝」などの表書きで、丁寧なメッセージを添えて送ることで、会場に足を運べなくても気持ちが伝わります。こうした非対面での贈り方においても、見た目の格式や清潔感が重要視されるため、祝用の金封の上品な意匠が好まれます。慶事にふさわしいデザインが選ばれているため、どのような場面でも安心して使用することができ、品位を保ちながら贈り物としての体裁を整えることが可能です。 金封(仏用)を使用する場面 表書き(献辞)に使用する「御佛前」は亡くなった方が成仏(じょうぶつ)した仏様の前にという意味合いがあり、「御霊前」は亡くなった方の御霊(みたま)の前にという意味合いがあります。仏教界では亡くなって御霊となった故人は忌明けをもって成仏するとの教えから、通夜、葬儀・告別式から忌明け直前までの法要には「御霊前」を、忌明け法要以降の全ての法要には「御佛前」を用いることになっています。但し、浄土真宗に限り、死とともに仏となって浄土に生まれ変わるとの教えから、通夜、葬儀・告別式から「御佛前」を用いることになっています。 尚、仏式ではあるが宗旨が不明という場合は「御香奠」として持参するのが無難です。神道では、故人は御霊となり、霊璽[れいじ]に移って後は神となるとの教えから、弔い事の儀式全般に「御霊前」や「御神前」を用いることが出来ます。キリスト教では、故人は霊魂となって神に召されるとの教えから、「御霊前」は弔い事の儀式全般に用いることが出来ます。通夜や葬儀に参列する際、会場で受付にて香典を渡す場面では、落ち着いた色合いで格式ある金封が、贈り手の誠意を表す手段として重宝されます。特に急な訃報に接した際、駆けつける時間が限られるなかであっても、心を込めた金封を持参することで、形式と気持ちの両面から弔意をきちんと伝えることができます。さらに、法要の場面でもこの金封は活躍します。初七日や四十九日、一周忌・三回忌といった法要の際に、施主や遺族への供物代わりに現金を包んで渡す場合、弔事用の正式な封筒として信頼を持って使用できます。特に、親族やごく近しい関係者が集う場面では、簡素ながらも品位を保った金封がふさわしく、場に合った礼節を表現するアイテムとして役立ちます。最近では、遠方での葬儀や法要に参列が難しい場合でも、現金書留で香典を送るケースが増えており、その際にも適切な金封を使用することがマナーとして重要視されています。また、職場関係での弔事においても活用機会が多く、部署やチームとして連名で香典を包む際にも、落ち着きと格式を兼ね備えた金封は好まれます。会社関係の葬儀に参列する場合、取引先や上司の家族に対しても失礼のない印象を与えるため、正しい形式の金封選びは特に重要です。適切な表書きと氏名の記入を行い、丁寧に手渡すことで、社会人としてのマナーを守った対応となります。
4290 円 (税込 / 送料別)

のし 熨斗 熨斗袋 不祝儀 袋 香奠 お香典 ご香典 香典 香典袋 お通夜 通夜 葬式 葬儀 お葬式 御仏前 お仏前 御佛前 お布施 お霊前 御霊前 慶弔用品 慶弔袋 仏事 金封 お布施 冠婚葬祭特上のし袋 万型 黄水引 黄枠 無字 御布施 御佛前 奉書紙 | ササガワ のし 熨斗 熨斗袋 不祝儀 袋 香奠 お香典 ご香典 香典 香典袋 お通夜 通夜 葬式 葬儀 お葬式 御仏前 お仏前 御佛前 お霊前 御霊前 慶弔用品 慶弔袋 仏事 金封 仏教 お悔み お悔やみ 封筒
【入り数】10枚袋入×20冊箱入 【サイズ】縦183mm×横92mm 【材質】奉書紙(100g/m2) ※封かんテープ付き 万型(黄水引・黄枠)のし袋の基本知識 万型(黄水引)のし袋とは万型のし袋は、告別式や葬儀など弔事の場で活躍するのし袋です。黄水引の印刷がされており、お札を折らずに入れる事ができる183mm×92mmの万型サイズ。封をする際にのりが必要なくテープを剥がしてワンタッチで封かんが出来る便利な封かんテープ付き。万型(黄枠)のし袋とは万型(黄枠)のし袋は、祝水引に準ずる用い方をするもので、水引が省略されていることから祝水引では仰々しいとする場合に用いるもので、記念品・賞品・景品・粗品などに用いられます。黄棒の印刷がされており、お札を折らずに入れる事ができる183mm×92mmの万型サイズ。封をする際にのりが必要なくテープを剥がしてワンタッチで封かんが出来る便利な封かんテープ付き。 タイプ品番 黄水引 無字6-2761 黄枠 御布施6-2771 黄水引 御佛前6-2741万型(黄水引・黄枠)のし袋の使い方 万型(黄水引)のし袋のマナー黄色の水引は本来は関西の大阪・京都・神戸・奈良の都市部に限り、各宗教共通に通夜・葬儀告別式・法要時の際に、喪家に対して贈る弔慰品や喪家よりの香奠返しの粗品に用いられていたものですが、現在では「佛水引」の蓮絵なしと同様に、法要時に「佛水引」では喪の意味合いが強過ぎるとの理由で、「黄水引」を用いる地区が増加してきています。仏教以外の神道やキリスト教の通夜・葬儀告別式・法要時の際には、「仏」のイメージが強い「佛水引」は避けて、「黄水引」を用いる方が適切です。いざというときに必要な仏用ののし袋は常用品としてもおすすめです。のし袋の表側には、贈り手の気持を表すために表書きを施します。表書きには「御悔み」「御香奠」などの文字を書き、贈り手の名前ものし袋に書く必要がありますが、その際は、「御布施」「御香料」といった表書きよりも少し小さめに名前を記載することを心掛けましょう。 タイプ品番 黄水引 無字6-2761 黄枠 御布施6-2771 黄水引 御佛前6-2741 万型(黄水引・黄枠)のし袋の使い方の例 表書き(献辞)に使用する「御佛前」は亡くなった方が成仏(じょうぶつ)した仏様の前にという意味合いがあり、「御霊前」は亡くなった方の御霊(みたま)の前にという意味合いがあります。仏教界では亡くなって御霊となった故人は忌明けをもって成仏するとの教えから、通夜、葬儀・告別式から忌明け直前までの法要には「御霊前」を、忌明け法要以降の全ての法要には「御佛前」を用いることになっています。但し、浄土真宗に限り、死とともに仏となって浄土に生まれ変わるとの教えから、通夜、葬儀・告別式から「御佛前」を用いることになっています。 尚、仏式ではあるが宗旨が不明という場合は「御香奠」として持参するのが無難です。神道では、故人は御霊となり、霊璽[れいじ]に移って後は神となるとの教えから、弔い事の儀式全般に「御霊前」や「御神前」を用いることが出来ます。キリスト教では、故人は霊魂となって神に召されるとの教えから、「御霊前」は弔い事の儀式全般に用いることが出来ます。「御布施」の記載がされたのし袋は弔事(お葬式や法事)の際に、寺院・僧侶への謝礼を渡す場合での使用がおすすめです。
6820 円 (税込 / 送料別)
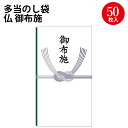
のし袋 金封 水引 熨斗 熨斗袋 不祝儀 袋 お布施 御布施 仏事 佛 お寺 供養 お彼岸 御供え お礼 奉書 水引 お金 封筒 中袋多当のし袋 仏 御布施 奉書紙 6-2683 ササガワ | のし袋 金封 水引 熨斗 熨斗袋 不祝儀 袋 お布施 御布施 仏事 佛 お寺 供養 お彼岸 御供え お礼 奉書 水引 お金 封筒 中袋
【入り数】1枚袋入×50枚箱入【サイズ】本体-縦190mm×横106mm、中袋(封筒)-縦177mm×横90mm【材質】奉書紙(110g/m2)奉書紙を使用したオーソドックスな多当のし袋。裏面には金額、住所、電話番号の書く欄があります。付属の中袋にも住所、氏名、金額を入れる枠があります。※本折ではございません。※裏面には金額、住所、電話番号の書く欄があります。付属の中袋にも住所、氏名、金額を入れる枠があります。多当のし袋のマナー 蓮が入ったものは、仏教の通夜・葬儀告別式時の際に、喪家に対して贈る弔慰金に用いられるものです。蓮の絵のないものは、仏教・神道・キリスト教など各宗教共通に通夜・葬儀告別式・法要時の際に、喪家に対して贈る弔慰金に用いられます。なお、仏教の通夜・葬儀告別式時に「蓮絵入」を用いても、法要時に「蓮絵入」では喪の意味合いが強過ぎるとの理由で、「蓮絵なし」や「黄水引」を用いる場合があります。いざというときに必要な仏用ののし袋は常用品としてもおすすめです。のし袋にお札を入れる際、お札の方向に特別な決まりはありませんが、中袋を表から見てお札の人物の顔が上になる様に入れると良いとされています。 のし袋の表側には、贈り手の気持を表すために表書きを施します。表書きには「御香料」「御香奠」などの文字を書き、贈り手の名前ものし袋に書く必要がありますが、こちらは「御布施」のプリントがされているので表書きよりも少し小さめに名前を記載することを心掛けましょう。また、こちらののし袋は裏面に金額、住所、電話番号を書く欄がありますので記入しましょう。中袋の表側には包んだ金額を記載し、中袋の裏側には贈り手の名前と住所を書きます。 多当のし袋の使い方の例 あわじ結びののし袋は、結び目が簡単にほどけないことから、「一度きりであってほしい」という気持ちを込めて用いられます。表書き(献辞)に使用する「御霊前」は亡くなった方の御霊(みたま)の前にという意味合いがあり、「御佛前」は亡くなった方が成仏(じょうぶつ)した仏様の前にという意味合いがあります。仏教界では亡くなって御霊となった故人は忌明けをもって成仏するとの教えから、通夜、葬儀・告別式から忌明け直前までの法要には「御霊前」を、忌明け法要以降の全ての法要には「御佛前」を用いることになっています。但し、浄土真宗に限り、死とともに仏となって浄土に生まれ変わるとの教えから、通夜、葬儀・告別式から「御佛前」を用いることになっています。 尚、仏式ではあるが宗旨が不明という場合は「御香奠」として持参するのが無難です。神道では、故人は御霊となり、霊璽[れいじ]に移って後は神となるとの教えから、弔い事の儀式全般に「御霊前」や「御神前」を用いることが出来ます。キリスト教では、故人は霊魂となって神に召されるとの教えから、「御霊前」は弔い事の儀式全般に用いることが出来ます。
6600 円 (税込 / 送料別)

香奠 お香典 ご香典 香典 香典袋 お通夜 通夜 葬式 葬儀 お葬式 御仏前 ご仏前 御佛前 お霊前 御香奠 お悔み 寄付 香典返し 仏事 お布施 お礼 献金 寄添料 弔意 贈答 葬儀特上のし袋 万型 仏 200枚入 奉書紙 ササガワ | 仏事 無字 御佛前 御仏前 御霊前 御香典 供養 法要 葬式 通夜 のし袋 のし 万型 奉書 上質 業務用 大容量 のし 熨斗 熨斗袋 不祝儀 袋 慶弔用品 慶弔袋 仏事 金封 仏教 お悔み お悔やみ 封筒 冠婚葬祭 供花
【入り数】10枚袋入×20冊箱入 【サイズ】縦183mm×横92mm 【材質】奉書紙(100g/m2) ※封かんテープ付き 万型(結切)のし袋の基本知識 万型(結切)のし袋とは万型のし袋は、告別式や葬儀など弔事の場で活躍するのし袋です。結び切り水引飾りの印刷がされており、お札を折らずに入れる事ができる183mm×92mmの万型サイズ。封をする際にのりが必要なくテープを剥がしてワンタッチで封かんが出来る便利な封かんテープ付き。 タイプ品番 無字6-2770 御佛前6-2792 御香奠6-2793 御霊前6-2788万型(結切)のし袋の使い方 万型(結切)のし袋のマナー蓮の絵が入ったものは、仏教の通夜・葬儀告別式・法要時の際に、喪家に対して贈る弔慰品や喪家よりの香奠返しの粗品に用いられるものです。蓮の絵のないものは、仏教・神道・キリスト教など各宗教共通に通夜・葬儀告別式・法要時の際に、喪家に対して贈る弔慰品や喪家よりの香奠返しの粗品に用いられます。尚、仏教の通夜・葬儀告別式時に「蓮絵入」を用いても、法要時に「蓮絵入」では喪の意味合いが強過ぎるとの理由で、「蓮絵なし」や「黄水引」を用いる場合があります。いざというときに必要な仏用ののし袋は常用品としてもおすすめです。のし袋の表側には、贈り手の気持を表すために表書きを施します。表書きには「御悔み」「御香奠」などの文字を書き、贈り手の名前ものし袋に書く必要がありますが、その際は、「御布施」「御香料」といった表書きよりも少し小さめに名前を記載することを心掛けましょう。 タイプ品番 無字6-2770 御佛前6-2792 御香奠6-2793 御霊前6-2788 万型(結切)のし袋の使い方の例 結切(結切り)ののし袋は、結び目が固く結ばれていて簡単にほどけないことから、「一度きりであってほしい」という気持ちを込めて用いられます。表書き(献辞)に使用する「御霊前」は亡くなった方の御霊(みたま)の前にという意味合いがあり、「御佛前」は亡くなった方が成仏(じょうぶつ)した仏様の前にという意味合いがあります。仏教界では亡くなって御霊となった故人は忌明けをもって成仏するとの教えから、通夜、葬儀・告別式から忌明け直前までの法要には「御霊前」を、忌明け法要以降の全ての法要には「御佛前」を用いることになっています。但し、浄土真宗に限り、死とともに仏となって浄土に生まれ変わるとの教えから、通夜、葬儀・告別式から「御佛前」を用いることになっています。 尚、仏式ではあるが宗旨が不明という場合は「御香奠」として持参するのが無難です。神道では、故人は御霊となり、霊璽[れいじ]に移って後は神となるとの教えから、弔い事の儀式全般に「御霊前」や「御神前」を用いることが出来ます。キリスト教では、故人は霊魂となって神に召されるとの教えから、「御霊前」は弔い事の儀式全般に用いることが出来ます。
6820 円 (税込 / 送料別)
