「ホビー > アート・美術品・骨董品・民芸品」の商品をご紹介します。

手摺木版で忠実に復刻した作品です■龍香堂■「劉長青」復刻木版浮世絵 葛飾北斎『富嶽百景 登龍の不二(青)』
外寸(約):430×320mm 絵サイズ:350×240mm 技法(種別):木版画 紙質:和紙 ●世界的芸術家、葛飾北斎。その『富嶽百景』中の『登龍の不二』です。雲を呼び、今まさに富士山を昇らんとする龍。下部の隅に龍を配置し、素材をかなり削ぎ落とした事により、龍の勢いが更に増して感じられる作品です。龍香堂と親交の有る版画研究室から買い取りました。北斎の描いた富士の自然な美を、手摺木版で忠実に復刻した作品です。 ☆当品は「変わり摺り」として版画で彩色したものです。 ◎当品は和紙1枚の状態です。額飾しておりません。 ※画像3は版木の一部と裏面の画像です。版画用染料が裏写りしているのは、印刷ではないことの証しです。 ●北斎が七十歳を過ぎて刊行された『富嶽三十六景』は、当時、富士信仰が盛んだった事もあり巷で大変な人気となった。その好評を受け刊行されたものが三十六景の続編ともいうべき『富嶽百景』である。『富嶽三十六景』が一枚絵で多色摺りであるのに対し、『富嶽百景』は三巻・102図からなる和綴じ本で、墨の濃淡のみの二色摺りである。当時の風物や人々の営みを、富士を交えスケッチ風に描かれており、この精巧な仕上がりからは、老いてなお並々ならぬ情熱と創作意欲が感じられる。北斎七十五歳頃の刊行と言われている。 ※製作者プロフィール 【劉 長青】(りゅう ちょうせい) 1955年 7月9日中国山東省生まれ。 中国山東省工芸美術学院絵画専業卒業。中国北京中央美術学院版画学部版画専業修了。中国政府派遣版画研究のため来日(東京芸術大学版画研究室)。「中国版画展」「世界版画展」「美術展覧」等において入選、受賞。 ※1995年・中国政府に「特殊貢献の優秀人材」の称号を受ける。 2001年・中国政府派遣再来日(東京芸術大学版画研究室、客員研究員) 現在は、東京芸術大学美術学部版画研究室、客員研究員。中国済南日報社高級編輯(教授職)。中国版画家協会会員・山東省版画家協会副会長・済南市版画学会会長。山東省新聞美術家協会副主席・山東建築工程大学芸術デザイン学部客員教授。 作品収蔵(略) : 栃木県足利学校(孔子記念館)・アメリカ・ポーランド・スウェーデン・スペイン・フランス・中国美術館・中国神州版画博物館・広東美術館・山東省美術館・四川省美術館等。※当商品は定形外郵便で発送致します。送料は、重量50~100g(規格外)220円をお願い致します。 ※代引き発送を御希望の場合は、諸費用で1000円をお願いしております。 ※当方から合計金額等のメールを送信後、1週間以内に御振り込み、もしくは御返信を頂けなかった場合はキャンセルとさせて頂きます。 ※こちらの商品を御注文頂きます時に、支払方法を「代引発送」にされますと、楽天から自動送信されますメールにはシステム上、代引き料金が350円と記載される事が御座います。この場合は龍香堂から改めまして合計金額をお知らせさせて頂きますので、必ずご確認下さいますようお願い致します。
11000 円 (税込 / 送料別)
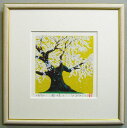
吉岡浩太郎 絵画 版画 風水 絵 大樹 桜風水開運版画30243 桜咲く吉岡浩太郎
作品名桜咲く 作家名吉岡浩太郎 ○作品詳細 作品の種類シルクスクリーン版画 作品の詳細エディション800部/作家サイン 絵サイズ15.0X15.0センチ 額縁サイズ32.0X32.0センチ 額縁のタイプアルミ製デザインフレーム/アクリルガラス付/マット額装※ブラウンタイプ・ホワイトタイプの2タイプからお選びください。 ○吉岡浩太郎プロフィール(2代目) 11960年山口県に生まれる。 1989年岐阜県展・市展入選 デザイン博記念NACC展TGC特別賞 1991年中部二科展デザイン特選 日本デザイナー学院最優秀賞 1992年二科展デザイン奨励賞 渡欧 1993年二科展デザイン特選 中部二科展デザイン彩画堂賞 1995年孔版画コンクール金賞 個展 1996年二科展デザイン奨励賞 中部二科展外遊賞 1997年個展 1998年二科会デザイン部会友推挙 個展 1999年孔版画コンクール金賞 個展 2001年二科展デザイン会友賞 2004年中部二科EXPACT賞 2005年愛・地球博会場にてワークショップ開催 2006年日韓グラフィックアート展出品 2008年中・日国際交流展出品 北京故宮博物院 2010年個展・グループ展開催 2013年横濱・グッズ001横浜市長賞受賞 2014年NBC国際版画ビエンナーレ入選 2015年日立・カレンダーに採用 2016年2代目吉岡浩太郎に襲名 ○吉岡浩太郎版画作品について ◎吉岡浩太郎版画についてシルクスクリーンとジグレスクリーンの2種類の版画技法によって制作されています。 ・シルクスクリーン版画とは、絹の繊細な織布の上に製版し、熟達した高度な摺り技術により 一色ごとに丹念に摺りあげていく多色刷版画です。 ・ジグレスクリーン版画とは、デジタル技法による精密機器を利用したアートでコンピュータにより 色彩分析を行いプリントされています。さらに、耐光性を強まるためにシルクスクリーンによる 表面処理がされています。 ◎エディションとは、作品左下にある限定数をいいます。分母が刷り数で分子が通し番号です。 通し番号に価値の違いはありません。また、追加再販には、Sまたは’があります。 APナンバーは作家所有のエディションナンバーです。
6600 円 (税込 / 送料別)

手摺木版で忠実に復刻した作品です■龍香堂■「劉長青」復刻木版浮世絵 葛飾北斎『富嶽百景 登龍の不二(朱)』
外寸(約):430×320mm 絵サイズ:350×240mm 技法(種別):木版画 紙質:和紙 ●世界的芸術家、葛飾北斎。その『富嶽百景』中の『登龍の不二』です。雲を呼び、今まさに富士山を昇らんとする龍。下部の隅に龍を配置し、素材をかなり削ぎ落とした事により、龍の勢いが更に増して感じられる作品です。龍香堂と親交の有る版画研究室から買い取りました。北斎の描いた富士の自然な美を、手摺木版で忠実に復刻した作品です。 ☆当品は「変わり摺り」として版画で彩色したものです。 ◎当品は和紙1枚の状態です。額飾しておりません。 ※画像3は版木の一部と裏面の画像です。版画用染料が裏写りしているのは、印刷ではないことの証しです。 ●北斎が七十歳を過ぎて刊行された『富嶽三十六景』は、当時、富士信仰が盛んだった事もあり巷で大変な人気となった。その好評を受け刊行されたものが三十六景の続編ともいうべき『富嶽百景』である。『富嶽三十六景』が一枚絵で多色摺りであるのに対し、『富嶽百景』は三巻・102図からなる和綴じ本で、墨の濃淡のみの二色摺りである。当時の風物や人々の営みを、富士を交えスケッチ風に描かれており、この精巧な仕上がりからは、老いてなお並々ならぬ情熱と創作意欲が感じられる。北斎七十五歳頃の刊行と言われている。 ※製作者プロフィール 【劉 長青】(りゅう ちょうせい) 1955年 7月9日中国山東省生まれ。 中国山東省工芸美術学院絵画専業卒業。中国北京中央美術学院版画学部版画専業修了。中国政府派遣版画研究のため来日(東京芸術大学版画研究室)。「中国版画展」「世界版画展」「美術展覧」等において入選、受賞。 ※1995年・中国政府に「特殊貢献の優秀人材」の称号を受ける。 2001年・中国政府派遣再来日(東京芸術大学版画研究室、客員研究員) 現在は、東京芸術大学美術学部版画研究室、客員研究員。中国済南日報社高級編輯(教授職)。中国版画家協会会員・山東省版画家協会副会長・済南市版画学会会長。山東省新聞美術家協会副主席・山東建築工程大学芸術デザイン学部客員教授。 作品収蔵(略) : 栃木県足利学校(孔子記念館)・アメリカ・ポーランド・スウェーデン・スペイン・フランス・中国美術館・中国神州版画博物館・広東美術館・山東省美術館・四川省美術館等。※当商品は定形外郵便で発送致します。送料は、重量50~100g(規格外)220円をお願い致します。 ※代引き発送を御希望の場合は、諸費用で1000円をお願いしております。 ※当方から合計金額等のメールを送信後、1週間以内に御振り込み、もしくは御返信を頂けなかった場合はキャンセルとさせて頂きます。 ※こちらの商品を御注文頂きます時に、支払方法を「代引発送」にされますと、楽天から自動送信されますメールにはシステム上、代引き料金が350円と記載される事が御座います。この場合は龍香堂から改めまして合計金額をお知らせさせて頂きますので、必ずご確認下さいますようお願い致します。
11000 円 (税込 / 送料別)
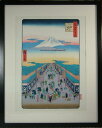
額に入れた状態なので、すぐに飾ることが出来ます。■龍香堂■「劉長青」復刻木版 歌川広重浮世絵『する賀てふ』額装済
額サイズ:425×525×厚35mm 絵サイズ:240×370mm 重さ:約2050g 技法(種別):木版画 紙質:和紙 ●世界的浮世絵師、歌川広重。その『名所江戸百景』中の『する賀てふ』です。龍香堂と親交の有る版画研究室から買い取りました。広重の描いた自然な美を、手摺木版で忠実に復刻した作品です。 ◎こちらは額に入れた状態なので、すぐに飾ることが出来ます。 ※画像3は、作品の裏面と使用した版木です。版画用染料が裏写りしているのは、印刷ではないことの証しです。 ●歌川広重(Hiroshige Utagawa)江戸の下級武士・八代洲河岸火消屋敷の同心、安藤源右衛門の子として誕生、天保3年(1832年)秋、幕府の行列(御馬進献の使)に加わって上洛(京都まで東海道往復の旅)する機会を得たとされる。天保4年(1833年)には傑作といわれる『東海道五十三次絵』が生まれた。この作品は遠近法が用いられ、風や雨を感じさせる立体的な描写など、絵そのものの良さに加えて、当時の人々があこがれた外の世界を垣間見る手段としても、大変好評を博した。広重の作品は、ヨーロッパやアメリカでは、大胆な構図などとともに、青色、特に藍色の美しさで評価が高い。欧米では「ジャパンブルー」、あるいはフェルメール・ブルー(ラピスラズリ)になぞらえて「ヒロシゲブルー」とも呼ばれる。19世紀後半のフランスに発した印象派の画家たちや、アール・ヌーヴォーの芸術家たちに大きな影響をあたえたとされ、当時ジャポニスムの流行を生んだ要因のひとつともされている。 【作品解説】名所江戸百景『する賀てふ』(するがちょう) する賀てふ(駿河町)とは、一直線先に富士山が見えたので付けられた町名だという。江戸一番の繁盛店「越後屋(三越)」の並びには、行きかう武士や女中などが生き生きと描かれており、現在へと続く位置的比較も見られて面白い。前景に広がる江戸商業の繁華街と、その道の先、即ち画面頂上にそびえる勇壮な富士山とも相まってとても御目出度い構図である。 ※製作者プロフィール 【劉 長青】(りゅう ちょうせい) 1955年 7月9日中国山東省生まれ。 中国山東省工芸美術学院絵画専業卒業。中国北京中央美術学院版画学部版画専業修了。中国政府派遣版画研究のため来日(東京芸術大学版画研究室)。「中国版画展」「世界版画展」「美術展覧」等において入選、受賞。 ※1995年・中国政府に「特殊貢献の優秀人材」の称号を受ける。 2001年・中国政府派遣再来日(東京芸術大学版画研究室、客員研究員) 現在は、東京芸術大学美術学部版画研究室、客員研究員。 中国済南日報社高級編輯(教授職)。 中国版画家協会会員・山東省版画家協会副会長・済南市版画学会会長。山東省新聞美術家協会副主席・山東建築工程大学芸術デザイン学部客員教授。 作品収蔵(略) : 栃木県足利学校(孔子記念館)・アメリカ・ポーランド・スウェーデン・スペイン・フランス・中国美術館・中国神州版画博物館・広東美術館・山東省美術館・四川省美術館等。※当商品の通常発送は日本郵便株式会社の「ゆうパック」とさせて頂きます。◎ゆうパックは発送先により送料が変わります。この場合は当方から改めまして合計金額をお知らせさせて頂きますので、必ずご確認下さいますようお願い致します◎ ※代引き発送を御希望の場合は、諸費用で1000円をお願いしております。 ※当方から合計金額等のメールを送信後、1週間以内に御振り込み、もしくは御返信を頂けなかった場合はキャンセルとさせて頂きます。 ※こちらの商品を御注文頂きます時に、支払方法を「代引発送」にされますと、楽天から自動送信されますメールにはシステム上、代引き料金が350円と記載される事が御座います。この場合は龍香堂から改めまして合計金額をお知らせさせて頂きますので、必ずご確認下さいますようお願い致します。
16500 円 (税込 / 送料別)

送料無料 吉岡浩太郎 絵画 版画 絵 花火【三々サイズ】版画3337 想い出の花火送料無料 吉岡浩太郎
作品名想い出の花火 作家名吉岡浩太郎 ○作品詳細 作品の種類シルクスクリーン版画 作品の詳細エディション500部/作家サイン 絵サイズ40.9X31.8センチ 額縁サイズ62.5X47.5センチ 額縁のタイプアルミ製デザインフレーム/アクリルガラス付/マット額装※ブラウンタイプ・ホワイトタイプの2タイプからお選びください。 ○吉岡浩太郎プロフィール 1960年山口県に生まれる。 1989年岐阜県展・市展入選 デザイン博記念NACC展TGC特別賞 1991年中部二科展デザイン特選 日本デザイナー学院最優秀賞 1992年二科展デザイン奨励賞 渡欧 1993年二科展デザイン特選 中部二科展デザイン彩画堂賞 1995年孔版画コンクール金賞 個展 1996年二科展デザイン奨励賞 中部二科展外遊賞 1997年個展 1998年二科会デザイン部会友推挙 個展 1999年孔版画コンクール金賞 個展 2001年二科展デザイン会友賞 2004年中部二科EXPACT賞 2005年愛・地球博会場にてワークショップ開催 2006年日韓グラフィックアート展出品 2008年中・日国際交流展出品 北京故宮博物院 2010年個展・グループ展開催 2013年横濱・グッズ001横浜市長賞受賞 2014年NBC国際版画ビエンナーレ入選 2015年日立・カレンダーに採用 2016年2代目吉岡浩太郎に襲名 2001年東京絵画フェスティバル出品 ○吉岡浩太郎版画作品について ◎吉岡浩太郎版画についてシルクスクリーンとジグレスクリーンの2種類の版画技法によって制作されています。 ・シルクスクリーン版画とは、絹の繊細な織布の上に製版し、熟達した高度な摺り技術により 一色ごとに丹念に摺りあげていく多色刷版画です。 ・ジグレスクリーン版画とは、デジタル技法による精密機器を利用したアートでコンピュータにより 色彩分析を行いプリントされています。さらに、耐光性を強まるためにシルクスクリーンによる 表面処理がされています。 ◎エディションとは、作品左下にある限定数をいいます。分母が刷り数で分子が通し番号です。 通し番号に価値の違いはありません。また、追加再販には、Sまたは’があります。 APナンバーは作家所有のエディションナンバーです。
15800 円 (税込 / 送料込)
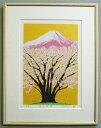
吉岡浩太郎 絵画 版画 風水 絵 大樹 桜 富士山風水開運版画SDL47 富士満開吉岡浩太郎
○ショップコメント富士と大樹桜は、金運、家運隆盛に最適な開運画といわれています。 作品名 富士満開 作家名 吉岡浩太郎 ○作品詳細 作品の種類 シルクスクリーン版画 作品の詳細 エディション500部/作家サイン 絵サイズ 35.4X24.2センチ 額縁サイズ 53.0X41.5センチ 額縁のタイプ アルミ製デザインフレーム/アクリルガラス付/マット額装※ブラウンタイプ・ホワイトタイプの2タイプからお選びください。 ここがポイント! 満開の桜咲く大樹は家運隆盛の象徴とされています。金色に輝く空は、金運を招きくといわれています。 ○吉岡浩太郎プロフィール(2代目) 1960年山口県に生まれる。 1989年岐阜県展・市展入選 デザイン博記念NACC展TGC特別賞 1991年中部二科展デザイン特選 日本デザイナー学院最優秀賞 1992年二科展デザイン奨励賞 渡欧 1993年二科展デザイン特選 中部二科展デザイン彩画堂賞 1995年孔版画コンクール金賞 個展 1996年二科展デザイン奨励賞 中部二科展外遊賞 1997年個展 1998年二科会デザイン部会友推挙 個展 1999年孔版画コンクール金賞 個展 2001年二科展デザイン会友賞 2004年中部二科EXPACT賞 2005年愛・地球博会場にてワークショップ開催 2006年日韓グラフィックアート展出品 2008年中・日国際交流展出品 北京故宮博物院 2010年個展・グループ展開催 2013年横濱・グッズ001横浜市長賞受賞 2014年NBC国際版画ビエンナーレ入選 2015年日立・カレンダーに採用 2016年2代目吉岡浩太郎に襲名 ○吉岡浩太郎版画作品について ◎吉岡浩太郎版画についてシルクスクリーンとジグレスクリーンの2種類の版画技法によって制作されています。 ・シルクスクリーン版画とは、絹の繊細な織布の上に製版し、熟達した高度な摺り技術により 一色ごとに丹念に摺りあげていく多色刷版画です。 ・ジグレスクリーン版画とは、デジタル技法による精密機器を利用したアートでコンピュータにより 色彩分析を行いプリントされています。さらに、耐光性を強まるためにシルクスクリーンによる 表面処理がされています。 ◎エディションとは、作品左下にある限定数をいいます。分母が刷り数で分子が通し番号です。 通し番号に価値の違いはありません。また、追加再販には、Sまたは’があります。 APナンバーは作家所有のエディションナンバーです。
15000 円 (税込 / 送料込)

手摺木版で忠実に復刻した作品です。■龍香堂■☆「劉長青」復刻木版 歌川広重浮世絵『原 朝之富士』
外寸:433×302mm 印面サイズ:383×253mm 技法(種別):木版画 紙質:和紙 世界的浮世絵師、歌川広重。その『東海道五十三次』中の『原 朝之富士』です。龍香堂と親交の有る版画研究室から買い取りました。広重の描いた自然な美を、手摺木版で忠実に復刻した作品です。 ※画像3、左は裏面の画像、右は使用した版木です。版画用染料が裏写りしているのは、印刷ではないことの証しです。 ●歌川広重(Hiroshige Utagawa)江戸の下級武士・八代洲河岸火消屋敷の同心、安藤源右衛門の子として誕生、天保3年(1832年)秋、幕府の行列(御馬進献の使)に加わって上洛(京都まで東海道往復の旅)する機会を得たとされる。天保4年(1833年)には傑作といわれる『東海道五十三次絵』が生まれた。この作品は遠近法が用いられ、風や雨を感じさせる立体的な描写など、絵そのものの良さに加えて、当時の人々があこがれた外の世界を垣間見る手段としても、大変好評を博した。広重の作品は、ヨーロッパやアメリカでは、大胆な構図などとともに、青色、特に藍色の美しさで評価が高い。欧米では「ジャパンブルー」、あるいはフェルメール・ブルー(ラピスラズリ)になぞらえて「ヒロシゲブルー」とも呼ばれる。19世紀後半のフランスに発した印象派の画家たちや、アール・ヌーヴォーの芸術家たちに大きな影響をあたえたとされ、当時ジャポニスムの流行を生んだ要因のひとつともされている。 【作品解説】東海道五十三次『原 朝之富士』(はら あさのふじ) 一番目を引くのは、風景を囲む枠から富士の頂上が飛び出ている優美で大胆な構図である。富士を仰ぎ見る母娘や供の者、旅人が足を止め、振り返って眺めたほどの去りがたい風景には、朝日に白雪が紅に染まり、街道の沼地には白鷺、遠い西の空は藍色に晴れ渡っている。人物の着衣と下草だけに見せた藍と草色だけの色彩も、この絵の感じを出す力として大きい。 ※製作者プロフィール 【劉 長青】(りゅう ちょうせい) 1955年 7月9日中国山東省生まれ。 中国山東省工芸美術学院絵画専業卒業。中国北京中央美術学院版画学部版画専業修了。中国政府派遣版画研究のため来日(東京芸術大学版画研究室)。「中国版画展」「世界版画展」「美術展覧」等において入選、受賞。 ※1995年・中国政府に「特殊貢献の優秀人材」の称号を受ける。 2001年・中国政府派遣再来日(東京芸術大学版画研究室、客員研究員) 現在は、東京芸術大学美術学部版画研究室、客員研究員。 中国済南日報社高級編輯(教授職)。 中国版画家協会会員・山東省版画家協会副会長・済南市版画学会会長。 山東省新聞美術家協会副主席・山東建築工程大学芸術デザイン学部客員教授。 作品収蔵(略) : 栃木県足利学校(孔子記念館)・アメリカ・ポーランド・スウェーデン・スペイン・フランス・中国美術館・中国神州版画博物館・広東美術館・山東省美術館・四川省美術館等。※当商品は定形外郵便で発送致します。送料は、重量50~100g(規格外)220円をお願い致します。 ※代引き発送を御希望の場合は、諸費用で1000円をお願いしております。 ※当方から合計金額等のメールを送信後、1週間以内に御振り込み、もしくは御返信を頂けなかった場合はキャンセルとさせて頂きます。 ※こちらの商品を御注文頂きます時に、支払方法を「代引発送」にされますと、楽天から自動送信されますメールにはシステム上、代引き料金が350円と記載される事が御座います。この場合は龍香堂から改めまして合計金額をお知らせさせて頂きますので、必ずご確認下さいますようお願い致します。
11000 円 (税込 / 送料別)
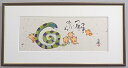
絵 日本画 墨絵 内山斉放【アートバーゲン会場】9,900円女流書家・内山斉放の描く墨彩画今年は一緒にあそぼうよ
○ショップコメント 女流書家の心あたたまる墨彩画作品です。 作品名 今年は一緒にあそぼうよ 作家名 内山斉放 ○作品詳細 作品の種類 墨彩日本画 作品サイズ 17.0X44.0センチ 作品の詳細 落款印・サイン 額縁サイズ 32.0X62.0センチ 額縁の詳細 アルミ製デザイン額・マット・アクリル付※額縁選択可 ○作家プロフィール 内山 斉放(うちやま せいほう) 埼玉県在住。 静岡県浜北市(現在の浜松市)生まれ。 清水草舟先生に師事し前衛書道を学ぶ。 その後、現代書芸院松田朴伝先生に師事し創作書道・墨象を学ぶ。 西部書作家協会展で毎日新聞社賞を受賞。 1980年 染色技術・水墨画・日本画・洋画を学び、独自の手法「創作手書き染め」を確立 1985年 福岡市で「創作手書き染め」として初の個展を開催 1986年 デパートにおける初の個展を大丸百貨店で開催 以降、三越・伊勢丹で毎年個展を開催 1994年 アメリカミシガン州にて日本文化を紹介するためグループ展に参加、書の実演を行う。 1996年 中国北京市で「創作手書き染め」の個展と交流会を実施 2001年 オーストラリア・ゴールドコーストで3人展開催 「創作手書き染め」「茶道」「折り紙」の実演 2002年 陽泰院(浜松市)の本堂に40枚の襖絵を描く。 2006年 イタリア・ナポリで日・伊文化協会協賛の個展を開催 2007年 三越仙台店、銀座店、丸善日本橋店にて個展を開催 現在は毎年三越デパートを中心とした個展と「手書き染め教室」を主催。 ギフト対応
9900 円 (税込 / 送料込)
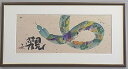
絵 日本画 墨絵 内山斉放【アートバーゲン会場】9,900円女流書家・内山斉放の描く墨彩画歡
○ショップコメント 女流書家の心あたたまる墨彩画作品です。 作品名 歡・かん 作家名 内山斉放 ○作品詳細 作品の種類 墨彩日本画 作品サイズ 19.0X47.0センチ 作品の詳細 落款印・サイン 額縁サイズ 32.0X62.0センチ 額縁の詳細 アルミ製デザイン額・マット・アクリル付※額縁選択可 ○作家プロフィール 内山 斉放(うちやま せいほう) 埼玉県在住。 静岡県浜北市(現在の浜松市)生まれ。 清水草舟先生に師事し前衛書道を学ぶ。 その後、現代書芸院松田朴伝先生に師事し創作書道・墨象を学ぶ。 西部書作家協会展で毎日新聞社賞を受賞。 1980年 染色技術・水墨画・日本画・洋画を学び、独自の手法「創作手書き染め」を確立 1985年 福岡市で「創作手書き染め」として初の個展を開催 1986年 デパートにおける初の個展を大丸百貨店で開催 以降、三越・伊勢丹で毎年個展を開催 1994年 アメリカミシガン州にて日本文化を紹介するためグループ展に参加、書の実演を行う。 1996年 中国北京市で「創作手書き染め」の個展と交流会を実施 2001年 オーストラリア・ゴールドコーストで3人展開催 「創作手書き染め」「茶道」「折り紙」の実演 2002年 陽泰院(浜松市)の本堂に40枚の襖絵を描く。 2006年 イタリア・ナポリで日・伊文化協会協賛の個展を開催 2007年 三越仙台店、銀座店、丸善日本橋店にて個展を開催 現在は毎年三越デパートを中心とした個展と「手書き染め教室」を主催。 ギフト対応
9900 円 (税込 / 送料込)
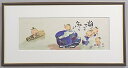
絵 日本画 墨絵 内山斉放【アートバーゲン会場】9,900円女流書家・内山斉放の描く墨彩画誰がやったか知らないよ
○ショップコメント 女流書家の心あたたまる墨彩画作品です。 作品名 誰がやったか知らないよ 作家名 内山斉放 ○作品詳細 作品の種類 墨彩日本画 作品サイズ 16.0X45.0センチ 作品の詳細 落款印・サイン 額縁サイズ 32.0X62.0センチ 額縁の詳細 木製額グリーン・マット・紙合わせ箱 ○作家プロフィール 内山 斉放(うちやま せいほう) 埼玉県在住。 静岡県浜北市(現在の浜松市)生まれ。 清水草舟先生に師事し前衛書道を学ぶ。 その後、現代書芸院松田朴伝先生に師事し創作書道・墨象を学ぶ。 西部書作家協会展で毎日新聞社賞を受賞。 1980年 染色技術・水墨画・日本画・洋画を学び、独自の手法「創作手書き染め」を確立 1985年 福岡市で「創作手書き染め」として初の個展を開催 1986年 デパートにおける初の個展を大丸百貨店で開催 以降、三越・伊勢丹で毎年個展を開催 1994年 アメリカミシガン州にて日本文化を紹介するためグループ展に参加、書の実演を行う。 1996年 中国北京市で「創作手書き染め」の個展と交流会を実施 2001年 オーストラリア・ゴールドコーストで3人展開催 「創作手書き染め」「茶道」「折り紙」の実演 2002年 陽泰院(浜松市)の本堂に40枚の襖絵を描く。 2006年 イタリア・ナポリで日・伊文化協会協賛の個展を開催 2007年 三越仙台店、銀座店、丸善日本橋店にて個展を開催 現在は毎年三越デパートを中心とした個展と「手書き染め教室」を主催。 ギフト対応
9900 円 (税込 / 送料込)
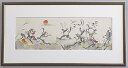
絵 日本画 墨絵 内山斉放【アートバーゲン会場】9,900円女流書家・内山斉放の描く墨彩画月が出たでた
○ショップコメント 女流書家の心あたたまる墨彩画作品です。 作品名 月が出たでた 作家名 内山斉放 ○作品詳細 作品の種類 墨彩日本画 作品サイズ 16.0X48.0センチ 作品の詳細 落款印・サイン 額縁サイズ 32.0X62.0センチ 額縁の詳細 アルミ製デザイン額・マット・アクリル付※額縁選択可 ○作家プロフィール 内山 斉放(うちやま せいほう) 埼玉県在住。 静岡県浜北市(現在の浜松市)生まれ。 清水草舟先生に師事し前衛書道を学ぶ。 その後、現代書芸院松田朴伝先生に師事し創作書道・墨象を学ぶ。 西部書作家協会展で毎日新聞社賞を受賞。 1980年 染色技術・水墨画・日本画・洋画を学び、独自の手法「創作手書き染め」を確立 1985年 福岡市で「創作手書き染め」として初の個展を開催 1986年 デパートにおける初の個展を大丸百貨店で開催 以降、三越・伊勢丹で毎年個展を開催 1994年 アメリカミシガン州にて日本文化を紹介するためグループ展に参加、書の実演を行う。 1996年 中国北京市で「創作手書き染め」の個展と交流会を実施 2001年 オーストラリア・ゴールドコーストで3人展開催 「創作手書き染め」「茶道」「折り紙」の実演 2002年 陽泰院(浜松市)の本堂に40枚の襖絵を描く。 2006年 イタリア・ナポリで日・伊文化協会協賛の個展を開催 2007年 三越仙台店、銀座店、丸善日本橋店にて個展を開催 現在は毎年三越デパートを中心とした個展と「手書き染め教室」を主催。 ギフト対応
9900 円 (税込 / 送料込)
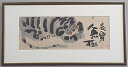
絵 日本画 墨絵 内山斉放【アートバーゲン会場】9,9000円女流書家・内山斉放の描く墨彩画無極・むきょく
○ショップコメント 女流書家の心あたたまる墨彩画作品です。 作品名 無極・むきょく 作家名 内山斉放 ○作品詳細 作品の種類 墨彩日本画 作品サイズ 16.5X45.0センチ 作品の詳細 落款印・サイン 額縁サイズ 32.0X62.0センチ 額縁の詳細 アルミ製デザイン額・マット・アクリル付※額縁選択可 ○作家プロフィール 内山 斉放(うちやま せいほう) 埼玉県在住。 静岡県浜北市(現在の浜松市)生まれ。 清水草舟先生に師事し前衛書道を学ぶ。 その後、現代書芸院松田朴伝先生に師事し創作書道・墨象を学ぶ。 西部書作家協会展で毎日新聞社賞を受賞。 1980年 染色技術・水墨画・日本画・洋画を学び、独自の手法「創作手書き染め」を確立 1985年 福岡市で「創作手書き染め」として初の個展を開催 1986年 デパートにおける初の個展を大丸百貨店で開催 以降、三越・伊勢丹で毎年個展を開催 1994年 アメリカミシガン州にて日本文化を紹介するためグループ展に参加、書の実演を行う。 1996年 中国北京市で「創作手書き染め」の個展と交流会を実施 2001年 オーストラリア・ゴールドコーストで3人展開催 「創作手書き染め」「茶道」「折り紙」の実演 2002年 陽泰院(浜松市)の本堂に40枚の襖絵を描く。 2006年 イタリア・ナポリで日・伊文化協会協賛の個展を開催 2007年 三越仙台店、銀座店、丸善日本橋店にて個展を開催 現在は毎年三越デパートを中心とした個展と「手書き染め教室」を主催。 ギフト対応
9900 円 (税込 / 送料込)
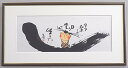
絵 日本画 墨絵 内山斉放【アートバーゲン会場】9,900円女流書家・内山斉放の描く墨彩画日々楽しく日々豊かに
○ショップコメント 女流書家の心あたたまる墨彩画作品です。 作品名 日々楽しく日々豊かに 作家名 内山斉放 ○作品詳細 作品の種類 墨彩日本画 作品サイズ 18.0X47.0センチ 作品の詳細 落款印・サイン 額縁サイズ 32.0X62.0センチ 額縁の詳細 アルミ製デザイン額・マット・アクリル付※額縁選択可 ○作家プロフィール 内山 斉放(うちやま せいほう) 埼玉県在住。 静岡県浜北市(現在の浜松市)生まれ。 清水草舟先生に師事し前衛書道を学ぶ。 その後、現代書芸院松田朴伝先生に師事し創作書道・墨象を学ぶ。 西部書作家協会展で毎日新聞社賞を受賞。 1980年 染色技術・水墨画・日本画・洋画を学び、独自の手法「創作手書き染め」を確立 1985年 福岡市で「創作手書き染め」として初の個展を開催 1986年 デパートにおける初の個展を大丸百貨店で開催 以降、三越・伊勢丹で毎年個展を開催 1994年 アメリカミシガン州にて日本文化を紹介するためグループ展に参加、書の実演を行う。 1996年 中国北京市で「創作手書き染め」の個展と交流会を実施 2001年 オーストラリア・ゴールドコーストで3人展開催 「創作手書き染め」「茶道」「折り紙」の実演 2002年 陽泰院(浜松市)の本堂に40枚の襖絵を描く。 2006年 イタリア・ナポリで日・伊文化協会協賛の個展を開催 2007年 三越仙台店、銀座店、丸善日本橋店にて個展を開催 現在は毎年三越デパートを中心とした個展と「手書き染め教室」を主催。 ギフト対応
9900 円 (税込 / 送料込)

春陽会会員 全道展会員 北海道版画界に大きな影響を与える北岡 文雄「雪の白川郷(世界遺産条約登録地シリーズNo,6)」木版画 北海道版画界に大きな影響を与える 小竹美術 真作保証
商品詳細 【 作者 】 北岡 文雄(キタオカ フミオ) 【タイトル】 雪の白川郷(世界遺産条約登録地シリーズNo,6) 【 技法 】 木版画 【制作年】 1996年作 【限定番号】 ed,106/200 【作品寸法】 縦54.8×横39.8cm 【額縁寸法】 縦80.5×横62cm 【作品状態】 ほぼ良好 【額縁状態】 良好 【付属品】 ガラスあり、箱あり 【作者プロフィール】春陽会会員、全道展会員 1918 東京生まれ 1939 平塚運一から木版画を学ぶ 1941 東京美術学校油画科卒 1943 日本版画協会会員 1951 春陽会会員 1955 ヨーロッパに留学(?56まで) 1956 帰国後妻の故郷札幌に一時滞在 1956 全道展会員 1969 北海道立美術館の「北海道秀作美術展」で賞候補賞(?70) 1971 ソ連画家同盟・ソ日協会の招きで訪ソ、モスクワ東方民族博物館で個展 1978 台北市国家画廊で個展 1980 北京中央美術学院の招きで木版画講習会開催 1987 北海道立近代美術館の「美術北海道100年展」出品 1993 北海道新聞社より「ミュージアム(13)・北岡文雄-光と風の版風景」を刊行 1993 北海道立近代美術館で「北岡文雄の世界展」開催 1997 北海道立近代美術館コレクション100選に選ばれる 1998 北海道立帯広美術館の「美術北海道20世紀展」に出品 2003 北海道新聞社編の「画集北海道・海のある風景」に作品掲載 2007 肺炎のため死去 ◆56年フランスから帰国後、妻幽子の郷里札幌に滞在。その間北海道の版画界に大きな影響を与える。一時、抽象や幻想的な版画を試みたが、60年以降は写実を基調とした木版画を多彩にくりひろげ現代に至る。また木版画を通して国際交流を図っている。 ■作品収蔵:東京国立近代美術館、北海道立近代美術館、ボストン美術館
52650 円 (税込 / 送料別)

トルコ・イスタンブールを代表する、世界で最も美しいモスク絵画 北岡文雄 木版画 『朝焼けのブルーモスク』 人々 宗教 建造物 木 空 雲 風景 外国風景 幻想的 明るい 美術品 アート きたおかふみお
トルコ・イスタンブールを代表する、世界で最も美しいモスク青い装飾タイルやステンドグラスで彩られ、白地に青の色調の美しさからブルーモスクと呼ばれるスルタンアフメト・モスク。世界遺産であるイスタンブール歴史地域の歴史的建造物群のひとつ。1990年制作、自筆サイン、限定130部技法:木版画絵のサイズ:縦55×横40cm額のサイズ:高さ77×幅63×奥行き3cm作品の状態:良好です保護箱:合わせ箱北岡文雄(きたおかふみお / KITAOKA Fumio)<略歴・情報>1918東京生まれ1939平塚運一から木版画を学ぶ1941東京美術学校油画科卒1943日本版画協会会員1951春陽会会員1955ヨーロッパに留学('56まで)1956帰国後妻の故郷札幌に一時滞在1956全道展会員1969北海道立美術館の「北海道秀作美術展」で賞候補賞('70)1971ソ連画家同盟・ソ日協会の招きで訪ソ、モスクワ東方民族博物館で個展1978台北市国家画廊で個展1980北京中央美術学院の招きで木版画講習会開催1987北海道立近代美術館の「美術北海道100年展」に出品1993北海道新聞社より「ミュージアム(13)・北岡文雄-光と風の版風景」を刊行1993北海道立近代美術館で「北岡文雄の世界展」開催1997北海道立近代美術館コレクション100選に選ばれる1998北海道立帯広美術館の「美術北海道20世紀I展」に出品2003北海道新聞社編の「画集北海道・海のある風景」に作品掲載2007肺炎のため死去<所属>日本版画協会会員、春陽会会員、全道展会員<特徴>'56年フランスから帰国後、妻幽子の郷里札幌に滞在。その間北海道の版画界に大きな影響を与える。一時抽象や幻想的な版画を試みたが、'60年以降は写実を基調とした木版画を多彩に繰り広げる。また木版画を通して国際交流を図る。<作品収蔵>東京国立近代美術館、北海道立近代美術館、ボストン美術館 他注意事項:お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
60000 円 (税込 / 送料込)

版画 絵画 こども 人物 かわいい いぬ 花 郷愁 人気 送料無料中島 潔 「 夏のいろ 」 リトグラフ 版画
■夏のいろ 風の画家として知られる中島潔画伯。 NHK「みんなのうた」のイメージ画や、書籍・絵本など 海外でも高い評価と人気を誇る作者の作品を 版画でお楽しみいただけます。 郷愁を誘う童画に心癒される素敵な作品です。 ■中島 潔 なかじまきよし 1943 佐賀県に生まれる 1964 広告会社に入社 アートディレクターとして多数の賞を受賞 1971 フランス・パリの美術学校に学ぶ 1982 NHK「みんなのうた」のイメージ画を手掛ける 1987 ボローニャ国際児童図書展でグラフィック賞受賞 1989 ワシントン洲百年祭を記念して作品を寄贈 1990 北京にて海外展開催 1999 NHKにて「郷愁・中島潔の世界」(春夏秋冬四部作)放送 2001 NHKにて「中島潔が描く金子みすゞの世界」放送 NHKにて「世界 わが心の旅セーヌ川・私を作った2人の 女」放送 2003 東京メトロ半蔵門線開通記念アートレリーフを制作 2007 東京・上野の森美術館にて「絵筆でつづる四半世紀展」 2008 NHK ラジオ深夜便の表紙絵を創刊以来描き続け 100号を迎える 2010 京都・清水寺成就院に襖絵46枚を奉納 NHKクローズアップ現代「風の画家・中島潔“いのち”を 描く」放送 2011 「清水寺成就院奉納襖絵ー生命の無常と輝き展ー」開催 2015 京都・六道珍皇寺にて「中島潔 地獄心音図完成特別 公開」展開催 作家名 中島 潔 題 名 夏のいろ 技 法 リトグラフ(石版画) 落 款 作者鉛筆サイン 監 修 中島 潔・創造教育センター・保証書付属 エディションナンバー 4/300 画面の寸法 縦344×横492mm 額縁の寸法 縦596×横727mm(実寸) 額縁の仕様 木製茶塗仕上げ 裏面に吊り金具・ひも付き マット 紙マット 額縁の窓 アクリル 箱 差し箱(黄袋付き) 工房・版元 あずま工芸株式会社
129800 円 (税込 / 送料込)
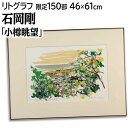
オレンジ色に染まった穏やかな海と空が見える、小樽の景色絵画 石岡剛 リトグラフ 版画 『小樽眺望』 木 海 空 街 風景 北海道風景 優しい 明るい 温もり 爽やか 生き生き 穏やか 美術品 アート いしおかごう
オレンジ色に染まった穏やかな海と空が見える、小樽の景色北海道小樽市の夕暮れ限定150部、自筆サイン画寸:26×38cm技法:リトグラフ額のサイズ:高さ46cm×幅61cm×奥行き3.0cm作品の状態:良好です石岡剛(いしおかごう / ISHIOKA Go)1945芦別生まれ1966武蔵野美術大学卒1976近代美術協会会員(のちに退会)1976ル・サロン入選('77、'81)1978道展で佳作賞(’80佳作賞)1982第1回 札幌そごう個展1986西ドイツ国際美術展で金賞1987イギリス選抜美術展で金賞1987近代美術協会展で会員優賞1988日中友好平和条約10周年記念展に出品(北京)1989日豪文化交流展に出品(メルボルン)1992バルセロナオリンピック記念スペインシリーズ3景リトグラフ制作1994石岡剛常設美術館 ル・プチ・ミュゼ「燦の館」完成1998財界さっぽろ表紙採用/北洋銀行カレンダー『窓辺の花』採用2002芦別市カナディアンワールド公園内「石岡剛の世界美術館」開館2006芦別市芸術文化交流館 芸術の郷「しんじょう」にアトリエ展示2014芦別市文化賞、芦別市功労賞*全国各地の有名百貨店で個展多数開催<特徴>繊細に描かれた風景の中に、燃えるような赤を大胆に配し、独特な世界観をつくりあげている。いきいきとした勢いがあり、ヨーロッパの空気を感じるお洒落な作品は、世界中のファンに愛されている。注意事項:お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
35000 円 (税込 / 送料込)

光の情景画家 百貨店個展多数 イラストレーター笹倉 鉄平「ブレストンコートにて」版画・限定品・本人直筆鉛筆サイン入 作品保証書付 光の情景画家 小竹美術 真作保証
商品詳細 【 作者 】 笹倉 鉄平(ササクラ テッペイ) 【タイトル】 ブレストンコートにて 【 技法 】 シルクスクリーン版画 【限定番号】 ed,33/295 【作品寸法】 縦43×横42.8cm 【額縁寸法】 縦76.5×横74.5cm 【作品状態】 良好 【額縁状態】 ほぼ良好(小傷若干あり) 【付属品】 アクリルあり、箱あり 【 備考 】 作品保証書付 【作者プロフィール】「光の情景画家」と呼ばれる 旅情と優しい光あふれるその情景画は、"心に安らぎをもたらす"絵として、老若男女幅広い層で多くの支持を得ている。また、画家デビュー以来、180作品以上の版画や、画集・詩画集・図録、DVD作品集等が出版され、ポスターやジグソーパズル、ポストカード、カレンダー等のアートグッズも人気が高い。近年では、フランス、中国、イタリア等にて開催した展覧会も成功を収め、日本人の美意識や優しさを、その美しい情景画を通して海外へ伝えている。 1954 兵庫県生まれ 1977 武蔵野美術大学商業デザイン科卒業後、グラフィックデザイナーを経て、イラストレーターとなる 1987 毎日新聞カラー別刷り版・裏表紙に、「Romantic Gallery(ドイツの街々を描いた)」シリーズを連載 1988 同紙に「ロマン色の街角(フランスの街々を描いた)」シリーズを連載 1990 東京、青山スパイラル・ギャラリーでの初個展開催を機に、画家としての制作、活動に専心 1998 「大丸ミュージアム東京」にて、初の美術館個展 2004 イタリアの芸術文芸都市のレカナーティ市主催による個展 2005 イタリア、フィレンツェ市主催による、パルテ・グエルファ宮での個展 2006 北京の国立中国美術館にて、劉長順氏と日中友好を掲げた二人展 2008 パリと京都にて、京都市の後援による「京都市パリ市姉妹都市締結50周年記念」個展 2015 京都とフィレンツェにて、両市後援のもと「京都・フィレンツェ姉妹都市提携50周年記念事業」の一環として個展 2021 東京「上野の森美術館」にて、画業30周年記念個展 ◆上記以外も1991年以降、国内有名百貨店等に於いて100回を超す個展開催
145200 円 (税込 / 送料別)

■送料無料対象外・送料別途必要■【中古】M▽趙無極 Zao Wou-ki ザオ・ウーキー 鹿内信隆に捧ぐ 版画 リトグラフ 額縁 ■送料無料対象外・送料別途必要■ (38393)
■■■店舗管理番号:その他 38393-SR■■■ ------------------------------------ ◇配送方法:ゆうパック170サイズ ◇送料:添付の送料表をご確認ください。 ◇お取り置き不可。ご注文から1週間程度での発送としそれ以上の保管はできません。 ◇ご購入前にプロフィール・商品ページをよくお読みの上ご不明点はお問い合わせ、解決後のご注文をお願いいたします。 ------------------------------------ ◆サイズ◆(約 mm) 額:幅660×奥行25×高さ845 窓:幅465×高さ635 ◆趙無極 ザオ・ウーキー◆ 1921年2月13日、中国北京に生まれた趙無極。1935年から6年間にわたり、杭州にある国立美術学校で中国絵画・西洋絵画を本格的に学び、1948年、妻子とともにフランスへ移住。活動の拠点をパリに置き、早くも1949年には画廊にて個展を開催しました。この個展がピカソやジョアン・ミロなどのビッグネームの目にとまり、趙無極は一躍有名に。以後、多くのアーティストたちから刺激を受ける形で、自らの作風を追求し続けました。2018年9月、サザビーズ香港にて実に74億円もの価格で落札されました。サザビーズ香港における最高落札額が更新された瞬間です。 (ネット情報・引用) 〇商品の状態:C 普通(多少の使用感有、傷凹み汚れ等有) ○保証対象は商品本体のみです。消耗品および付属品は保証対象外とさせていただきます。また付属品は写真に写っている物が全てです。交換・不足部品はご自身でご用意願います。 ○清掃しておりますがあくまで中古品でございます。写真には写りきらない傷・汚れ等ございます。予めご承知おきください。 ■■■返品特約及び保証期間について■■■ 保証期間は商品到着後8日以内とします。 ご注文後はお客様のご都合による返品及び売買契約の解除はお受けすることができません。 ただし商品に瑕疵・虚偽説明・不実記載・商品到着時著しく破損している場合のみ返品・返金を承ります。 (返品の際に必要となりますので保証期間内は梱包材の保管をお願いいたします。) 保証期間後の返品・返金・修理はいかなる場合もお受けできませんので商品到着後は速やかに確認をお願いいたします。 保証対象は商品代金・送料のみとし取り付け工事費、営業できなかった為に発生した損害等その他諸費用、またお客様にて手配して頂きました運送料金・店頭受け取りの際の交通費等につきましては保証対象外となります。 ご注文いただいた時点で上記の点をご了承いただいた事とさせていただきます。
330000 円 (税込 / 送料別)

笹倉鉄平がシルクスクリーンの版画で制作した絵画「ヴァイオリンの森に」を通販で販売しています。笹倉鉄平 ヴァイオリンの森に インテリア 絵画 シルクスクリーン 版画 プレゼント コレクション 新築祝い 開店祝い 新品額付き 国内送料無料 ■
画家名:笹倉鉄平 作品名:ヴァイオリンの森に 絵のサイズ:W52,5×H52,5cm 額装サイズ:W81×H82cm 版画の技法:シルクスクリーン サイン:作家直筆鉛筆サイン 納期:14日 笹倉鉄平さんがシルクスクリーンの版画で制作した絵画「ヴァイオリンの森に(In Violin Forest)」は、1994年に制作されたシルクスクリーンの版画です。 73版80色で、東京の「Kato Art Studio」という工房で制作されました。 このシルクスクリーンの版画の限定枚数はレギュラーエディション900部、ローマ数字バージョン500部、AP版(作家保存版)70部、 PP版(刷り師保存版)5部、HC(非売品)7部のトータル1482部のシルクスクリーンの版画が制作されました。 本作品は900部プリントされたレギュラーエディションのバージョンです。 2階の窓辺で男性が弾いているヴァイオリンの素晴らしい音色を皆が聞いている、そんなシチュエーションの絵画です。 じっとこの絵を見ているとヴァイオリンの音色が聞こえてきそうな、笹倉鉄平さんの素敵なシルクスクリーンの版画です。 制作されてから30年以上経過していますが、本作品は完璧な保存状態でシミや焼け、波打ち、色落ちなど一切ない新品同様の状態です。 ちなみに額は新品です。 笹倉鉄平さんがシルクスクリーンの版画で制作した絵画「ヴァイオリンの森に」をぜひご自宅のインテリアやコレクションの絵としてご購入ください。 笹倉鉄平 プロフィール 1954年兵庫県に生まれる。 1977年武蔵野美術大学商業デザイン科を卒業後、グラフィックデザイナーを経て、イラストレーターとなる。 1987年毎日新聞に「Romantic Gallery(ドイツの街々を描いた)」シリーズを連載する。 1988年毎日新聞に「ロマン色の街角(フランスの街々を描いた)」シリーズを連載する。 1990年青山スパイラル・ギャラリーでの絵画の初個展の開催を機に、画家としての制作活動に専心する。 1998年「大丸ミュージアム東京」にて絵画の個展を開催する。 2004年イタリアのレカナーティ市主催による絵画の個展を開催する。 2005年イタリア・フィレンツェ市主催によるパルテ・グエルファ宮での絵画の個展が開催される。 2006年北京の国立中国美術館にて劉長順氏と日中友好を掲げた絵画の二人展が開催される。 2008年パリと京都にて京都市の後援による「京都市パリ市姉妹都市締結50周年記念」の絵画の個展が開催される。 2015年京都とフィレンツェにて両市後援のもと「京都・フィレンツェ姉妹都市提携50周年記念事業」の一環として絵画の個展が開催される。
280000 円 (税込 / 送料込)

光の情景画家笹倉 鉄平「エヴァーグリーン」シルクスクリーン版画 限定サイン入り 光の情景画家 小竹美術 真作保証
商品詳細 【 作者 】 笹倉 鉄平(ササクラ テッペイ) 【タイトル】 エヴァーグリーン 【 技法 】 シルクスクリーン版画 【制作年】 2003年作 【限定番号】 ed,177/285 【作品寸法】 30号(縦43.5×横90.3cm) 【額縁寸法】 縦67×横112cm 【作品状態】 良好 【額縁状態】 良好 【付属品】 アクリルあり、箱あり 【作者プロフィール】 旅情と優しい光あふれるその情景画は、"心に安らぎをもたらす"絵として、老若男女幅広い層で多くの支持を得ている。 また、画家デビュー以来、180作品以上の版画や、画集・詩画集・図録、DVD作品集等が出版され、ポスターやジグソーパズル、ポストカード、カレンダー等のアートグッズも人気が高い。近年では、フランス、中国、イタリア等にて開催した展覧会も成功を収め、日本人の美意識や優しさを、その美しい情景画を通して海外へ伝えている。 1954 兵庫県生まれ 1977 武蔵野美術大学商業デザイン科卒業後、グラフィックデザイナーを経て、イラストレーターとなる 1987 毎日新聞カラー別刷り版・裏表紙に、「Romantic Gallery(ドイツの街々を描いた)」シリーズを連載 1988 同紙に「ロマン色の街角(フランスの街々を描いた)」シリーズを連載 1990 東京、青山スパイラル・ギャラリーでの初個展開催を機に、画家としての制作、活動に専心 1998 「大丸ミュージアム東京」にて、初の美術館個展 2004 イタリアの芸術文芸都市のレカナーティ市主催による個展 2005 イタリア、フィレンツェ市主催による、パルテ・グエルファ宮での個展 2006 北京の国立中国美術館にて、劉長順氏と日中友好を掲げた二人展 2008 パリと京都にて、京都市の後援による「京都市パリ市姉妹都市締結50周年記念」個展 2015 京都とフィレンツェにて、両市後援のもと「京都・フィレンツェ姉妹都市提携50周年記念事業」の一環として個展、上記以外も1991年以降、国内有名百貨店等に於いて100回を超す個展開催がある
660000 円 (税込 / 送料別)

光の情景画家笹倉 鉄平「エクリューズ浜」シルクスクリーン版画 限定サイン入り 光の情景画家 小竹美術 真作保証
商品詳細 【 作者 】 笹倉 鉄平(ササクラ テッペイ) 【タイトル】 エクリューズ浜 【 技法 】 シルクスクリーン版画 【制作年】 2006年作 【限定番号】 ed,278/285 【作品寸法】 30号(縦34×横90.8cm) 【額縁寸法】 縦56.5×横111cm 【作品状態】 良好 【額縁状態】 良好 【付属品】 アクリルあり、箱あり 【備考】 作品証明書付き 【作者プロフィール】 旅情と優しい光あふれるその情景画は、"心に安らぎをもたらす"絵として、老若男女幅広い層で多くの支持を得ている。 また、画家デビュー以来、180作品以上の版画や、画集・詩画集・図録、DVD作品集等が出版され、ポスターやジグソーパズル、ポストカード、カレンダー等のアートグッズも人気が高い。近年では、フランス、中国、イタリア等にて開催した展覧会も成功を収め、日本人の美意識や優しさを、その美しい情景画を通して海外へ伝えている。 1954 兵庫県生まれ 1977 武蔵野美術大学商業デザイン科卒業後、グラフィックデザイナーを経て、イラストレーターとなる 1987 毎日新聞カラー別刷り版・裏表紙に、「Romantic Gallery(ドイツの街々を描いた)」シリーズを連載 1988 同紙に「ロマン色の街角(フランスの街々を描いた)」シリーズを連載 1990 東京、青山スパイラル・ギャラリーでの初個展開催を機に、画家としての制作、活動に専心 1998 「大丸ミュージアム東京」にて、初の美術館個展 2004 イタリアの芸術文芸都市のレカナーティ市主催による個展 2005 イタリア、フィレンツェ市主催による、パルテ・グエルファ宮での個展 2006 北京の国立中国美術館にて、劉長順氏と日中友好を掲げた二人展 2008 パリと京都にて、京都市の後援による「京都市パリ市姉妹都市締結50周年記念」個展 2015 京都とフィレンツェにて、両市後援のもと「京都・フィレンツェ姉妹都市提携50周年記念事業」の一環として個展、上記以外も1991年以降、国内有名百貨店等に於いて100回を超す個展開催がある
385000 円 (税込 / 送料別)

光あふれる清明な色使いで、穏やかな志 賀高原の緑陰風景を描き続けた石川滋彦石川滋彦 山湖緑韻 志賀高原 油彩10号
作家名 石川滋彦 技法 キャンバスに油彩 絵サイズ 10号(縦45.5X横53.0cm) 絵の状態 良 好 額サイズ 縦68.7X横76.2cm 額の状態 ほぼ良好 サイン 石川滋彦油彩筆サイン 額の仕様 金装飾額縁 マット 麻布マット 格安卸価格税込297,000円 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 石川滋彦年譜(1909-1994) 1909 東京都麹町区麹町に洋画家石川欽一郎の長男と して生まれる 台北に移り台北師範付属小学校へ入学するが、 一学年一学期を終わり東京の番町小学校に転校 さらに小田原に移り、ついで鎌倉に転居 鎌倉師範付属小学校を卒業する 1922 神奈川県立湘南中学に入学 三学年一年間は関東大震災後の避難もかね、台 北一中に移るもまた湘南中学に戻り卒業 1927 東京美術学校(現東京芸術大学)西洋画科入学 岡田三郎助に師事 1929 第10回帝展に「湖畔の丘」を出品して入選 1932 東京美術学校西洋画科を卒業 同校研究科に入学 1935 光風会展光風賞受賞 1936 西洋美術史の矢代幸雄先生のもと研究科を修了 1938 第2回文展に「信濃の鍛冶屋」を出品し特選 (京都市立美術館所蔵) 1939 第3回文展に「迷彩する商船」を出品し特選 文展無鑑査、光風会会員となる 1940 海洋美術展に「入港準備」を出品し海軍大臣賞を 受ける 1942 東大工学部講師 海軍報道班員としてジャワに派遣され、戦争記 録画として「バタビア沖海戦」を描く 1943 北京へ旅行 海軍報道班員として第二南遣艦隊付と発令され ていたが、ジャカルタ海軍武官府に派遣され、 シンガポールとジャカルタを行き来する 1945 横須賀海兵団に召集 終戦でおわる 1947 学習院講師となる 第11回新制作展に出品、会員に推挙される 以後新制作展出品 1952 あらすか丸という貨物船で神戸を出港し西回り で南米へでかける 1955 明大工学部建築科講師となる 1956 船で出発、スエズ運河を通り10月はじめロン ドンに着く その後欧州各地をまわり翌年帰国し個展を開く 1957 欧州作品展を開催、以来ほぼ毎個展開催 1959 NHK教育テレビで絵画教室を一年間にわたり 放送 1960 志賀高原に度々取材 1966 カリフォルニア旅行、その後毎のように海外ス ケッチ旅 行に行く 晩年は初夏のアムステルダム運河風景を好んで 描いた 1975 画集「石川滋彦・人と作品」刊行 1986 「7月のアムステルダム」で第10回長谷川仁記念 賞受賞 1994 東京にて逝去 享年84歳石川滋彦山湖緑韻-志賀高原号 油彩10号 光あふれる清明な色使いで、穏やかな志 賀高原の緑陰風景を描き続けた石川滋彦
297000 円 (税込 / 送料込)

日本画革新の旗手として、斬新な発想と動的な描写で 新しい時代に対応する日本画をみずから創り上げた。加山又造 静物 木版画 1967年
作家名 加山又造 制作年 1967 技法 木版画 版数 15版70度摺 絵サイズ 縦31.5X横41.5cm 絵の状態 良 好 額サイズ 縦63.9X横53.1cm 額の状態 新 品 限定 87/100 額の仕様 金額縁 マット 白紙マット 格安卸価格税込99,360円 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 加山又造年譜(1927-2004) 1927 9月24日京都府京都市上京区相国寺東門前町 に西陣織の図案家加山勝也の子として生まれる 1944 京都市立美術工芸学校日本画科修了 1949 東京美術学校(現東京芸術大学)日本画科卒業 山本丘人に師事 創造美術展に初出品 1950 春季創造美術展に「自画像」「動物園」が初入選 研究会賞を受賞 1951 このから数年間動物をモチーフとする作品発表 1956 新制作協会会員となる 1967 第4回日本国際美術展で佳作受賞 1958 グッゲンハイム賞国際美術展で団体賞受賞 1961 ニューヨークのジャネットネスラー画廊で個展を開催 1965 琳派風の装飾屏風の制作を開始 次いで水墨画、裸婦を発表 1966 多摩美術大学日本画科教授に就任 (~1973、1977~1988) 1968 日航ボーイングLR機の機内壁面画を完成 1973 第5回日本芸術大賞受賞(新潮文芸振興会) 1974 「中央公論」表紙絵を制作(~1980) 1975 「加山又造展]が西武百貨店渋谷店で開催 (日本経済新聞社主催) 1978 東京国立近代美術館から依頼された紙本壁画[雪] [月][花]を完成 1980 《月光波濤》で第30回芸術選奨文部大臣賞受賞 1982 第1回美術文化振興協会賞受賞(美術文化振興協会) 1984 身延山久遠寺本堂の天井画《墨龍》と襖絵を完成 「加山又造天井画展」開催 (身延山久遠寺、読売新聞社主催) 1988 東京芸術大学美術学部教授に就任(~95) 「加山又造屏風絵展」が東京、京都、横浜 大阪の高島屋で開催(日本経済新聞社主催) 1990 世界の著名アーティストの手による「BMWアートカー」 シリーズの第9作目を完成 北京の中央美術学院より名誉教授の称号授与 1992 日本経済新聞「私の履歴書」に原稿執筆、1ヶ月 にわたり掲載 『白い画布 加山又造』として書籍化 (日本経済新聞社) 新東京国際空港第2旅客ターミナル出発ロビー 陶板壁画《日月四季》を完成 1993 「日本 加山又造美術作品精選展」が北京中国美術館 上海美術館で開催 「中国巡回帰国記念 加山又造展」開催 東京、京都、横浜、大阪の高島屋 (日本経済新聞社主催) 1994 「加山又造屏風絵展」開催 (東京、福岡、心斎橋、京都の大丸) 第43回神奈川文化賞芸術の部門受賞 1995 「KAYAMA MATAZO:NEW TRIUMPHSFOR OLD TRADITIONS」 がロンドンの大英博物館日本ギャラリーで開催 「加山又造展-版画と屏風による-1953~1996」開催 (松山、神戸、東京) 「今泉今右衛門・加山又造合作陶芸展」開催 (日本橋・壺中居) 東京芸術大学教授退官、名誉教授となる 1997 英国航空の新CI導入に際し、機体尾翼等のデザイン 原画[濤と鶴]を制作 文化功労者として顕彰される 京都臨済宗大本山天竜寺の法堂の天井画「雲龍」制作 1998 「やまと絵の心 加山又造展」開催 (東京国立近代美術館) 1999 井上靖文化賞受賞 2003 文化勲章を受賞 2004 4月6日東京都内にて肺炎のため逝去 享年76歳加山又造 静物(木版画) 大和絵や琳派等の古典に深く傾倒しながらその技術や 表現に学び、それに現代的な感覚が強く盛り込まれた 華麗な装飾美を加え、自己の世界に見事に再生した。
99360 円 (税込 / 送料込)

仏教の源流を遡り、シルクロードシリーズなどの 連作で日本画壇に清新の境地を開拓した平山郁夫平山郁夫 敦煌 絲綢之路 リトグラフ 平山郁夫直筆鉛筆署名 1990年 生前作 平山郁夫本人監修 しちゅうのみち
作家名 平山郁夫 制作年 1990 技法 リトグラフ 絵サイズ 縦32.0X横41.0cm 絵の状態 良 好 額サイズ 縦59X横69.1cm 額の状態 新 品 限定 300部 落款 朱落款 額の仕様 金額縁 マット 白紙マット 格安卸価格税込89,640円 この作品は平山郁夫先生ご存命中に作られたリトグラフです 平山郁夫先生ご本人が監修しております 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 平山郁夫年譜(1930-2009) 1930 6月15日広島県に生まれる 1947 東京美術学校日本画予科に入学 1952 東京美術学校日本画科を卒業 東京芸術大学美術学部日本画科副手就任 前田青邨に師事 1953 第38回院展に初入選 東京芸術大学日本画科助手となる 1955 日本美術院院友に推挙 1959 原爆の後遺症で制作面でも行き詰まっていたが、 第44回院展に「仏教伝来」を出品し、制作上の転 機となる 1960 第45回院展に「天山南路(夜)」を出品 仏伝シリーズの制作を始める 1961 第46回院展「入湟槃幻想」で日本美術院賞受賞 東京国立近代美術館買い上げ 日本美術院特待に推挙 1962 第47回院展の「受胎霊夢」で日本美術院賞受賞 第1回ユネスコ・フェローシップによリヨーロッパヘ留学 1963 第48回院展の「建立金剛心図」で奨励賞 (白寿賞・G賞)受賞 1964 日本美術院同人に推挙 第49回院展の「仏説長阿含経巻五」「続深海曼茶羅」 で文部大臣賞受賞 東京芸術大学美術学部日本画科講師となる 1966 東京芸術大学中世オリエント遺跡学術調査団に 参加しトルコヘ イヒララ渓谷の中世キリスト教寺院、修道院の 壁画模写に従事 1967 法隆寺金堂壁画再現事業に携わる 1968 中央アジアを旅行、仏教伝来の源流を訪ねる この旅行がシルクロードに情熱を傾ける発端となる 1969 東京芸術大学助教授となる 1970 日本美術院評議員に推挙 1973 東京芸術大学教授となる 高松塚古墳壁画の現状模写に従事 東京芸術大学イタリア初期ルネッサンス壁画調査団に参加 1975 日本美術家代表団の一員として初めて訪中 1976 第8回日本芸術大賞を受賞 中近東にて平山郁夫日本画展開催 (イラン・イラク・シリア・エジプト・トルコ) 1977 第11回仏教伝道文化賞を受賞する 1978 第63回院展「画禅院青邨先生還浄図」で内閣 総理大臣賞受賞 1979 アテネ・北京・広州にて平山郁夫日本画展開催 中国スケッチ旅行で初めて敦煌を訪れる 1981 日本美術院理事となる 1983 第1回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1984 外務省日本中国文化促進代表団に参加 1985 北京中央工芸美術学院外国人名誉教授となる 第2回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1987 第3回東京芸術大学敦煌学術調査団に団長と して参加 1988 東京芸術大学美術学部部長となる ユネスコ親善大使に任命される 文化財保護振興財団が発足理事に就任 1989 日本敦煌学術文化訪問団団長で敦煌遺跡訪問 東京芸術大学第6代学長となる 1990 ポロブドゥール遺跡と海のシルクロード取材 のため、インドネシアヘ 1991 「平山郁夫シルクロード展」開催 (フランス国立ギメ東洋美術館) フランス政府よりコマンドール勲章を授与される 1992 日中友好協会会長となる 早稲田大学名誉博士となる 1993 アンコール遺跡救済特別企画「平山郁夫の眼と 仕事」を開催 1994 黒部峡谷を取材 宇奈月町制施行40周年記念特別講演を行う 1995 第13回東美特別展に「幻の瀧」を始めとする 黒部峡谷取材作品を出品 東京芸術大学学長を満期退任する 1996 フランスよりレジオンドヌール勲章を授与される 日本美術院理事長に就任 1998 文化勲章を授与される 2000 奈良、薬師寺玄奘三蔵院「大唐西域壁画」完成 2001 東京芸術大学学長に再任される 日本美術院理事長 東京芸術大学学長 2005 東京芸術大学学長を退任 2009 12月2日死去 享年79歳 平山郁夫は、生涯を通じて150回以上も世界各地の 遺跡を訪問し取材や保護活動を展開してきましたその 中心となったのがシルクロードであり、仏教伝来の道 でした 東京藝術大学で教鞭をとり、作画に励む一方、ユネスコ 親善大使日本中国友好協会会長、日本美術院理事長、 日本育英会会長、芸術研究振興財団・文化財保護振興 財団各理事長などの要職を歴任しながら、公私にわた って展開した文化財保護活動は多岐にわたっています 主な事業だけでも、シルクロード周辺地域を中心とす る文化財・文化遺産の保護はもとより、美術工芸品や 建造物の保存修復に対する助成、伝統技術保持者等の 人材養成事業、芸術研究・文化財保存研究の奨励、海 外主要美術館が所蔵する日本古美術の修復援助、自然 災害や紛争による被災文化財の救出、そして芸術文化 振興への支援等枚挙に暇がありません それらの中でも、ユネスコ親善大使の時に実現した北朝鮮 高句麗古墳群の世界遺産登録をはじめ、アンコール遺 跡や敦煌石窟の保護活動、南京城壁の修復事業などに 対する助成活動、また、なお記憶に新しいバーミヤン 大仏の保護活動等は国際間の友好親善と平和運動に多 大な貢献をなし、世界的にもきわめて高い評価を受け ています こうした偉大な業績により、1998に文化勲章を授与さ れたほか、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、ア メリカ、フランス、バチカンなどの諸外国に於いても 数々の賞や勲章を受賞しています平山郁夫 敦煌(絲綢之路)(しちゅうのみち)みずからの被爆体験を原点とした平和への強い祈りは、生涯のテーマとなる。仏教の源流を遡る旅となり、それ は仏教を主題にした幻想的な作風となり、シルクロード シリーズなどの連作で日本画壇に清新の境地を開拓した (絲綢之路)(しちゅうのみち)は「絹の道」を意味し、 ユーラシア大陸の交易路網を指します。紀元前2世紀 から15世紀半ばまで活躍し、中国の都市と西方の諸 地域を結ぶ陸上交通路でした。絲綢とは絹布の意。
89640 円 (税込 / 送料込)

仏教の源流を遡り、シルクロードシリーズなどの 連作で日本画壇に清新の境地を開拓した平山郁夫平山郁夫 楼蘭 絲綢之路 リトグラフ 平山郁夫直筆鉛筆署名 1990年 生前作 平山郁夫本人監修 しちゅうのみち
作家名 平山郁夫 制作年 1990 技法 リトグラフ 絵サイズ 縦32.0X横41.0cm 絵の状態 良 好 額サイズ 縦59X横69.1cm 額の状態 新 品 限定 300部 落款 朱落款 額の仕様 金額縁 マット 白紙マット 格安卸価格税込89,640円 この作品は平山郁夫先生ご存命中に作られたリトグラフです 平山郁夫先生ご本人が監修しております 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 平山郁夫年譜(1930-2009) 1930 6月15日広島県に生まれる 1947 東京美術学校日本画予科に入学 1952 東京美術学校日本画科を卒業 東京芸術大学美術学部日本画科副手就任 前田青邨に師事 1953 第38回院展に初入選 東京芸術大学日本画科助手となる 1955 日本美術院院友に推挙 1959 原爆の後遺症で制作面でも行き詰まっていたが、 第44回院展に「仏教伝来」を出品し、制作上の転 機となる 1960 第45回院展に「天山南路(夜)」を出品 仏伝シリーズの制作を始める 1961 第46回院展「入湟槃幻想」で日本美術院賞受賞 東京国立近代美術館買い上げ 日本美術院特待に推挙 1962 第47回院展の「受胎霊夢」で日本美術院賞受賞 第1回ユネスコ・フェローシップによリヨーロッパヘ留学 1963 第48回院展の「建立金剛心図」で奨励賞 (白寿賞・G賞)受賞 1964 日本美術院同人に推挙 第49回院展の「仏説長阿含経巻五」「続深海曼茶羅」 で文部大臣賞受賞 東京芸術大学美術学部日本画科講師となる 1966 東京芸術大学中世オリエント遺跡学術調査団に 参加しトルコヘ イヒララ渓谷の中世キリスト教寺院、修道院の 壁画模写に従事 1967 法隆寺金堂壁画再現事業に携わる 1968 中央アジアを旅行、仏教伝来の源流を訪ねる この旅行がシルクロードに情熱を傾ける発端となる 1969 東京芸術大学助教授となる 1970 日本美術院評議員に推挙 1973 東京芸術大学教授となる 高松塚古墳壁画の現状模写に従事 東京芸術大学イタリア初期ルネッサンス壁画調査団に参加 1975 日本美術家代表団の一員として初めて訪中 1976 第8回日本芸術大賞を受賞 中近東にて平山郁夫日本画展開催 (イラン・イラク・シリア・エジプト・トルコ) 1977 第11回仏教伝道文化賞を受賞する 1978 第63回院展「画禅院青邨先生還浄図」で内閣 総理大臣賞受賞 1979 アテネ・北京・広州にて平山郁夫日本画展開催 中国スケッチ旅行で初めて敦煌を訪れる 1981 日本美術院理事となる 1983 第1回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1984 外務省日本中国文化促進代表団に参加 1985 北京中央工芸美術学院外国人名誉教授となる 第2回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1987 第3回東京芸術大学敦煌学術調査団に団長と して参加 1988 東京芸術大学美術学部部長となる ユネスコ親善大使に任命される 文化財保護振興財団が発足理事に就任 1989 日本楼蘭学術文化訪問団団長で楼蘭遺跡訪問 東京芸術大学第6代学長となる 1990 ポロブドゥール遺跡と海のシルクロード取材 のため、インドネシアヘ 1991 「平山郁夫シルクロード展」開催 (フランス国立ギメ東洋美術館) フランス政府よりコマンドール勲章を授与される 1992 日中友好協会会長となる 早稲田大学名誉博士となる 1993 アンコール遺跡救済特別企画「平山郁夫の眼と 仕事」を開催 1994 黒部峡谷を取材 宇奈月町制施行40周年記念特別講演を行う 1995 第13回東美特別展に「幻の瀧」を始めとする 黒部峡谷取材作品を出品 東京芸術大学学長を満期退任する 1996 フランスよりレジオンドヌール勲章を授与される 日本美術院理事長に就任 1998 文化勲章を授与される 2000 奈良、薬師寺玄奘三蔵院「大唐西域壁画」完成 2001 東京芸術大学学長に再任される 日本美術院理事長 東京芸術大学学長 2005 東京芸術大学学長を退任 2009 12月2日死去 享年79歳 平山郁夫は、生涯を通じて150回以上も世界各地の 遺跡を訪問し取材や保護活動を展開してきましたその 中心となったのがシルクロードであり、仏教伝来の道 でした 東京藝術大学で教鞭をとり、作画に励む一方、ユネスコ 親善大使日本中国友好協会会長、日本美術院理事長、 日本育英会会長、芸術研究振興財団・文化財保護振興 財団各理事長などの要職を歴任しながら、公私にわた って展開した文化財保護活動は多岐にわたっています 主な事業だけでも、シルクロード周辺地域を中心とす る文化財・文化遺産の保護はもとより、美術工芸品や 建造物の保存修復に対する助成、伝統技術保持者等の 人材養成事業、芸術研究・文化財保存研究の奨励、海 外主要美術館が所蔵する日本古美術の修復援助、自然 災害や紛争による被災文化財の救出、そして芸術文化 振興への支援等枚挙に暇がありません それらの中でも、ユネスコ親善大使の時に実現した北朝鮮 高句麗古墳群の世界遺産登録をはじめ、アンコール遺 跡や敦煌石窟の保護活動、南京城壁の修復事業などに 対する助成活動、また、なお記憶に新しいバーミヤン 大仏の保護活動等は国際間の友好親善と平和運動に多 大な貢献をなし、世界的にもきわめて高い評価を受け ています こうした偉大な業績により、1998に文化勲章を授与さ れたほか、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、ア メリカ、フランス、バチカンなどの諸外国に於いても 数々の賞や勲章を受賞しています平山郁夫 楼蘭(絲綢之路)(しちゅうのみち)みずからの被爆体験を原点とした平和への強い祈りは、生涯のテーマとなる。仏教の源流を遡る旅となり、それ は仏教を主題にした幻想的な作風となり、シルクロード シリーズなどの連作で日本画壇に清新の境地を開拓した (絲綢之路)(しちゅうのみち)は「絹の道」を意味し、 ユーラシア大陸の交易路網を指します。紀元前2世紀 から15世紀半ばまで活躍し、中国の都市と西方の諸 地域を結ぶ陸上交通路でした。絲綢とは絹布の意。
89640 円 (税込 / 送料込)
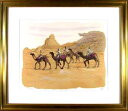
仏教の源流を遡り、シルクロードシリーズなどの 連作で日本画壇に清新の境地を開拓した平山郁夫平山郁夫 絲綢之路 リトグラフ 平山郁夫直筆鉛筆署名 1990年 生前作 平山郁夫本人監修 しちゅうのみち
作家名 平山郁夫 制作年 1990 技法 リトグラフ 絵サイズ 縦32.0X横41.0cm 絵の状態 良 好 額サイズ 縦59X横69.1cm 額の状態 新 品 限定 300部 落款 朱落款 額の仕様 金額縁 マット 白紙マット 格安卸価格税込113,400円 この作品は平山郁夫先生ご存命中に作られたリトグラフです 平山郁夫先生ご本人が監修しております 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 平山郁夫年譜(1930-2009) 1930 6月15日広島県に生まれる 1947 東京美術学校日本画予科に入学 1952 東京美術学校日本画科を卒業 東京芸術大学美術学部日本画科副手就任 前田青邨に師事 1953 第38回院展に初入選 東京芸術大学日本画科助手となる 1955 日本美術院院友に推挙 1959 原爆の後遺症で制作面でも行き詰まっていたが、 第44回院展に「仏教伝来」を出品し、制作上の転 機となる 1960 第45回院展に「天山南路(夜)」を出品 仏伝シリーズの制作を始める 1961 第46回院展「入湟槃幻想」で日本美術院賞受賞 東京国立近代美術館買い上げ 日本美術院特待に推挙 1962 第47回院展の「受胎霊夢」で日本美術院賞受賞 第1回ユネスコ・フェローシップによリヨーロッパヘ留学 1963 第48回院展の「建立金剛心図」で奨励賞 (白寿賞・G賞)受賞 1964 日本美術院同人に推挙 第49回院展の「仏説長阿含経巻五」「続深海曼茶羅」 で文部大臣賞受賞 東京芸術大学美術学部日本画科講師となる 1966 東京芸術大学中世オリエント遺跡学術調査団に 参加しトルコヘ イヒララ渓谷の中世キリスト教寺院、修道院の 壁画模写に従事 1967 法隆寺金堂壁画再現事業に携わる 1968 中央アジアを旅行、仏教伝来の源流を訪ねる この旅行がシルクロードに情熱を傾ける発端となる 1969 東京芸術大学助教授となる 1970 日本美術院評議員に推挙 1973 東京芸術大学教授となる 高松塚古墳壁画の現状模写に従事 東京芸術大学イタリア初期ルネッサンス壁画調査団に参加 1975 日本美術家代表団の一員として初めて訪中 1976 第8回日本芸術大賞を受賞 中近東にて平山郁夫日本画展開催 (イラン・イラク・シリア・エジプト・トルコ) 1977 第11回仏教伝道文化賞を受賞する 1978 第63回院展「画禅院青邨先生還浄図」で内閣 総理大臣賞受賞 1979 アテネ・北京・広州にて平山郁夫日本画展開催 中国スケッチ旅行で初めて敦煌を訪れる 1981 日本美術院理事となる 1983 第1回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1984 外務省日本中国文化促進代表団に参加 1985 北京中央工芸美術学院外国人名誉教授となる 第2回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1987 第3回東京芸術大学敦煌学術調査団に団長と して参加 1988 東京芸術大学美術学部部長となる ユネスコ親善大使に任命される 文化財保護振興財団が発足理事に就任 1989 日本楼蘭学術文化訪問団団長で楼蘭遺跡訪問 東京芸術大学第6代学長となる 1990 ポロブドゥール遺跡と海のシルクロード取材 のため、インドネシアヘ 1991 「平山郁夫シルクロード展」開催 (フランス国立ギメ東洋美術館) フランス政府よりコマンドール勲章を授与される 1992 日中友好協会会長となる 早稲田大学名誉博士となる 1993 アンコール遺跡救済特別企画「平山郁夫の眼と 仕事」を開催 1994 黒部峡谷を取材 宇奈月町制施行40周年記念特別講演を行う 1995 第13回東美特別展に「幻の瀧」を始めとする 黒部峡谷取材作品を出品 東京芸術大学学長を満期退任する 1996 フランスよりレジオンドヌール勲章を授与される 日本美術院理事長に就任 1998 文化勲章を授与される 2000 奈良、薬師寺玄奘三蔵院「大唐西域壁画」完成 2001 東京芸術大学学長に再任される 日本美術院理事長 東京芸術大学学長 2005 東京芸術大学学長を退任 2009 12月2日死去 享年79歳 平山郁夫は、生涯を通じて150回以上も世界各地の 遺跡を訪問し取材や保護活動を展開してきましたその 中心となったのがシルクロードであり、仏教伝来の道 でした 東京藝術大学で教鞭をとり、作画に励む一方、ユネスコ 親善大使日本中国友好協会会長、日本美術院理事長、 日本育英会会長、芸術研究振興財団・文化財保護振興 財団各理事長などの要職を歴任しながら、公私にわた って展開した文化財保護活動は多岐にわたっています 主な事業だけでも、シルクロード周辺地域を中心とす る文化財・文化遺産の保護はもとより、美術工芸品や 建造物の保存修復に対する助成、伝統技術保持者等の 人材養成事業、芸術研究・文化財保存研究の奨励、海 外主要美術館が所蔵する日本古美術の修復援助、自然 災害や紛争による被災文化財の救出、そして芸術文化 振興への支援等枚挙に暇がありません それらの中でも、ユネスコ親善大使の時に実現した北朝鮮 高句麗古墳群の世界遺産登録をはじめ、アンコール遺 跡や敦煌石窟の保護活動、南京城壁の修復事業などに 対する助成活動、また、なお記憶に新しいバーミヤン 大仏の保護活動等は国際間の友好親善と平和運動に多 大な貢献をなし、世界的にもきわめて高い評価を受け ています こうした偉大な業績により、1998に文化勲章を授与さ れたほか、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、ア メリカ、フランス、バチカンなどの諸外国に於いても 数々の賞や勲章を受賞しています平山郁夫 絲綢之路(しちゅうのみち)みずからの被爆体験を原点とした平和への強い祈りは、 生涯のテーマとなる。仏教の源流を遡る旅となり、それ は仏教を主題にした幻想的な作風となり、シルクロード シリーズなどの連作で日本画壇に清新の境地を開拓した 絲綢之路(しちゅうのみち)は「絹の道」を意味し、 ユーラシア大陸の交易路網を指します。紀元前2世紀 から15世紀半ばまで活躍し、中国の都市と西方の諸 地域を結ぶ陸上交通路でした。絲綢とは絹布の意。
113400 円 (税込 / 送料込)
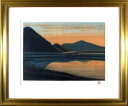
仏教の源流を遡り、シルクロードシリーズなどの 連作で日本画壇に清新の境地を開拓した平山郁夫平山郁夫 拉薩郊外 シルクロード古都幻想 銅版画 1979年 生前作 平山郁夫本人監修 さらこうがい 版画
作家名 平山郁夫 制作年 1979 技法 銅版画 絵サイズ 縦29.1X横41.2cm 絵の状態 良 好 額サイズ 縦59X横69.1cm 額の状態 新 品 限定 306/450 落款 朱落款 額の仕様 金額縁 マット 白紙マット 格安卸価格税込99,360円 この作品は平山郁夫先生ご存命中に作られた銅版画です 平山郁夫先生ご本人が監修しております 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 平山郁夫年譜(1930-2009) 1930 6月15日広島県に生まれる 1947 東京美術学校日本画予科に入学 1952 東京美術学校日本画科を卒業 東京芸術大学美術学部日本画科副手就任 前田青邨に師事 1953 第38回院展に初入選 東京芸術大学日本画科助手となる 1955 日本美術院院友に推挙 1959 原爆の後遺症で制作面でも行き詰まっていたが、 第44回院展に「仏教伝来」を出品し、制作上の転 機となる 1960 第45回院展に「天山南路(夜)」を出品 仏伝シリーズの制作を始める 1961 第46回院展「入湟槃幻想」で日本美術院賞受賞 東京国立近代美術館買い上げ 日本美術院特待に推挙 1962 第47回院展の「受胎霊夢」で日本美術院賞受賞 第1回ユネスコ・フェローシップによリヨーロッパヘ留学 1963 第48回院展の「建立金剛心図」で奨励賞 (白寿賞・G賞)受賞 1964 日本美術院同人に推挙 第49回院展の「仏説長阿含経巻五」「続深海曼茶羅」 で文部大臣賞受賞 東京芸術大学美術学部日本画科講師となる 1966 東京芸術大学中世オリエント遺跡学術調査団に 参加しトルコヘ イヒララ渓谷の中世キリスト教寺院、修道院の 壁画模写に従事 1967 法隆寺金堂壁画再現事業に携わる 1968 中央アジアを旅行、仏教伝来の源流を訪ねる この旅行がシルクロードに情熱を傾ける発端となる 1969 東京芸術大学助教授となる 1970 日本美術院評議員に推挙 1973 東京芸術大学教授となる 高松塚古墳壁画の現状模写に従事 東京芸術大学イタリア初期ルネッサンス壁画調査団に参加 1975 日本美術家代表団の一員として初めて訪中 1976 第8回日本芸術大賞を受賞 中近東にて平山郁夫日本画展開催 (イラン・イラク・シリア・エジプト・トルコ) 1977 第11回仏教伝道文化賞を受賞する 1978 第63回院展「画禅院青邨先生還浄図」で内閣 総理大臣賞受賞 1979 アテネ・北京・広州にて平山郁夫日本画展開催 中国スケッチ旅行で初めて敦煌を訪れる 1981 日本美術院理事となる 1983 第1回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1984 外務省日本中国文化促進代表団に参加 1985 北京中央工芸美術学院外国人名誉教授となる 第2回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1987 第3回東京芸術大学敦煌学術調査団に団長と して参加 1988 東京芸術大学美術学部部長となる ユネスコ親善大使に任命される 文化財保護振興財団が発足理事に就任 1989 日本楼蘭学術文化訪問団団長で楼蘭遺跡訪問 東京芸術大学第6代学長となる 1990 ポロブドゥール遺跡と海のシルクロード取材 のため、インドネシアヘ 1991 「平山郁夫シルクロード展」開催 (フランス国立ギメ東洋美術館) フランス政府よりコマンドール勲章を授与される 1992 日中友好協会会長となる 早稲田大学名誉博士となる 1993 アンコール遺跡救済特別企画「平山郁夫の眼と 仕事」を開催 1994 黒部峡谷を取材 宇奈月町制施行40周年記念特別講演を行う 1995 第13回東美特別展に「幻の瀧」を始めとする 黒部峡谷取材作品を出品 東京芸術大学学長を満期退任する 1996 フランスよりレジオンドヌール勲章を授与される 日本美術院理事長に就任 1998 文化勲章を授与される 2000 奈良、薬師寺玄奘三蔵院「大唐西域壁画」完成 2001 東京芸術大学学長に再任される 日本美術院理事長 東京芸術大学学長 2005 東京芸術大学学長を退任 2009 12月2日死去 享年79歳 平山郁夫は、生涯を通じて150回以上も世界各地の 遺跡を訪問し取材や保護活動を展開してきましたその 中心となったのがシルクロードであり、仏教伝来の道 でした 東京藝術大学で教鞭をとり、作画に励む一方、ユネスコ 親善大使日本中国友好協会会長、日本美術院理事長、 日本育英会会長、芸術研究振興財団・文化財保護振興 財団各理事長などの要職を歴任しながら、公私にわた って展開した文化財保護活動は多岐にわたっています 主な事業だけでも、シルクロード周辺地域を中心とす る文化財・文化遺産の保護はもとより、美術工芸品や 建造物の保存修復に対する助成、伝統技術保持者等の 人材養成事業、芸術研究・文化財保存研究の奨励、海 外主要美術館が所蔵する日本古美術の修復援助、自然 災害や紛争による被災文化財の救出、そして芸術文化 振興への支援等枚挙に暇がありません それらの中でも、ユネスコ親善大使の時に実現した北朝鮮 高句麗古墳群の世界遺産登録をはじめ、アンコール遺 跡や敦煌石窟の保護活動、南京城壁の修復事業などに 対する助成活動、また、なお記憶に新しいバーミヤン 大仏の保護活動等は国際間の友好親善と平和運動に多 大な貢献をなし、世界的にもきわめて高い評価を受け ています こうした偉大な業績により、1998に文化勲章を授与さ れたほか、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、ア メリカ、フランス、バチカンなどの諸外国に於いても 数々の賞や勲章を受賞しています平山郁夫 拉薩郊外(シルクロード古都幻想)(さらこうがい)みずからの被爆体験を原点とした平和への強い祈りは、 生涯のテーマとなる。仏教の源流を遡る旅となり、それ は仏教を主題にした幻想的な作風となり、シルクロード シリーズなどの連作で日本画壇に清新の境地を開拓した
99360 円 (税込 / 送料込)
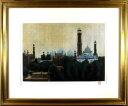
仏教の源流を遡り、シルクロードシリーズなどの 連作で日本画壇に清新の境地を開拓した平山郁夫平山郁夫 古都ラホール シルクロード古都幻想 銅版画 1979年 生前作 平山郁夫本人監修 版画
作家名 平山郁夫 制作年 1979 技法 銅版画 絵サイズ 縦29.1X横41.2cm 絵の状態 良 好 額サイズ 縦53.0X横64.2cm 額の状態 新 品 限定 306/450 落款 朱落款 額の仕様 金額縁 マット 白紙マット 格安卸価格税込99,360円 この作品は平山郁夫先生ご存命中に作られた銅版画です 平山郁夫先生ご本人が監修しております 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 平山郁夫年譜(1930-2009) 1930 6月15日広島県に生まれる 1947 東京美術学校日本画予科に入学 1952 東京美術学校日本画科を卒業 東京芸術大学美術学部日本画科副手就任 前田青邨に師事 1953 第38回院展に初入選 東京芸術大学日本画科助手となる 1955 日本美術院院友に推挙 1959 原爆の後遺症で制作面でも行き詰まっていたが、 第44回院展に「仏教伝来」を出品し、制作上の転 機となる 1960 第45回院展に「天山南路(夜)」を出品 仏伝シリーズの制作を始める 1961 第46回院展「入湟槃幻想」で日本美術院賞受賞 東京国立近代美術館買い上げ 日本美術院特待に推挙 1962 第47回院展の「受胎霊夢」で日本美術院賞受賞 第1回ユネスコ・フェローシップによリヨーロッパヘ留学 1963 第48回院展の「建立金剛心図」で奨励賞 (白寿賞・G賞)受賞 1964 日本美術院同人に推挙 第49回院展の「仏説長阿含経巻五」「続深海曼茶羅」 で文部大臣賞受賞 東京芸術大学美術学部日本画科講師となる 1966 東京芸術大学中世オリエント遺跡学術調査団に 参加しトルコヘ イヒララ渓谷の中世キリスト教寺院、修道院の 壁画模写に従事 1967 法隆寺金堂壁画再現事業に携わる 1968 中央アジアを旅行、仏教伝来の源流を訪ねる この旅行がシルクロードに情熱を傾ける発端となる 1969 東京芸術大学助教授となる 1970 日本美術院評議員に推挙 1973 東京芸術大学教授となる 高松塚古墳壁画の現状模写に従事 東京芸術大学イタリア初期ルネッサンス壁画調査団に参加 1975 日本美術家代表団の一員として初めて訪中 1976 第8回日本芸術大賞を受賞 中近東にて平山郁夫日本画展開催 (イラン・イラク・シリア・エジプト・トルコ) 1977 第11回仏教伝道文化賞を受賞する 1978 第63回院展「画禅院青邨先生還浄図」で内閣 総理大臣賞受賞 1979 アテネ・北京・広州にて平山郁夫日本画展開催 中国スケッチ旅行で初めて敦煌を訪れる 1981 日本美術院理事となる 1983 第1回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1984 外務省日本中国文化促進代表団に参加 1985 北京中央工芸美術学院外国人名誉教授となる 第2回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1987 第3回東京芸術大学敦煌学術調査団に団長と して参加 1988 東京芸術大学美術学部部長となる ユネスコ親善大使に任命される 文化財保護振興財団が発足理事に就任 1989 日本楼蘭学術文化訪問団団長で楼蘭遺跡訪問 東京芸術大学第6代学長となる 1990 ポロブドゥール遺跡と海のシルクロード取材 のため、インドネシアヘ 1991 「平山郁夫シルクロード展」開催 (フランス国立ギメ東洋美術館) フランス政府よりコマンドール勲章を授与される 1992 日中友好協会会長となる 早稲田大学名誉博士となる 1993 アンコール遺跡救済特別企画「平山郁夫の眼と 仕事」を開催 1994 黒部峡谷を取材 宇奈月町制施行40周年記念特別講演を行う 1995 第13回東美特別展に「幻の瀧」を始めとする 黒部峡谷取材作品を出品 東京芸術大学学長を満期退任する 1996 フランスよりレジオンドヌール勲章を授与される 日本美術院理事長に就任 1998 文化勲章を授与される 2000 奈良、薬師寺玄奘三蔵院「大唐西域壁画」完成 2001 東京芸術大学学長に再任される 日本美術院理事長 東京芸術大学学長 2005 東京芸術大学学長を退任 2009 12月2日死去 享年79歳 平山郁夫は、生涯を通じて150回以上も世界各地の 遺跡を訪問し取材や保護活動を展開してきましたその 中心となったのがシルクロードであり、仏教伝来の道 でした 東京藝術大学で教鞭をとり、作画に励む一方、ユネスコ 親善大使日本中国友好協会会長、日本美術院理事長、 日本育英会会長、芸術研究振興財団・文化財保護振興 財団各理事長などの要職を歴任しながら、公私にわた って展開した文化財保護活動は多岐にわたっています 主な事業だけでも、シルクロード周辺地域を中心とす る文化財・文化遺産の保護はもとより、美術工芸品や 建造物の保存修復に対する助成、伝統技術保持者等の 人材養成事業、芸術研究・文化財保存研究の奨励、海 外主要美術館が所蔵する日本古美術の修復援助、自然 災害や紛争による被災文化財の救出、そして芸術文化 振興への支援等枚挙に暇がありません それらの中でも、ユネスコ親善大使の時に実現した北朝鮮 高句麗古墳群の世界遺産登録をはじめ、アンコール遺 跡や敦煌石窟の保護活動、南京城壁の修復事業などに 対する助成活動、また、なお記憶に新しいバーミヤン 大仏の保護活動等は国際間の友好親善と平和運動に多 大な貢献をなし、世界的にもきわめて高い評価を受け ています こうした偉大な業績により、1998に文化勲章を授与さ れたほか、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、ア メリカ、フランス、バチカンなどの諸外国に於いても 数々の賞や勲章を受賞しています平山郁夫 古都ラホール(シルクロード古都幻想)みずからの被爆体験を原点とした平和への強い祈りは、 生涯のテーマとなる。仏教の源流を遡る旅となり、それ は仏教を主題にした幻想的な作風となり、シルクロード シリーズなどの連作で日本画壇に清新の境地を開拓した
99360 円 (税込 / 送料込)
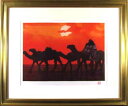
仏教の源流を遡り、シルクロードシリーズなどの 連作で日本画壇に清新の境地を開拓した平山郁夫平山郁夫 シリア砂漠の夕 シルクロード古都幻想 銅版画 1979年 生前作 平山郁夫本人監修 版画
作家名 平山郁夫 制作年 1979 技法 銅版画 絵サイズ 縦29.1X横41.2cm 絵の状態 良 好 額サイズ 縦53.3X横64.3cm 額の状態 新 品 限定 306/450 落款 朱落款 額の仕様 金額縁 マット 白紙マット 格安卸価格税込139,320円 この作品は平山郁夫先生ご存命中に作られた銅版画です 平山郁夫先生ご本人が監修しております 注意書き:モニター発色の具合により色合いが異なる場合がございます。 平山郁夫年譜(1930-2009) 1930 6月15日広島県に生まれる 1947 東京美術学校日本画予科に入学 1952 東京美術学校日本画科を卒業 東京芸術大学美術学部日本画科副手就任 前田青邨に師事 1953 第38回院展に初入選 東京芸術大学日本画科助手となる 1955 日本美術院院友に推挙 1959 原爆の後遺症で制作面でも行き詰まっていたが、 第44回院展に「仏教伝来」を出品し、制作上の転 機となる 1960 第45回院展に「天山南路(夜)」を出品 仏伝シリーズの制作を始める 1961 第46回院展「入湟槃幻想」で日本美術院賞受賞 東京国立近代美術館買い上げ 日本美術院特待に推挙 1962 第47回院展の「受胎霊夢」で日本美術院賞受賞 第1回ユネスコ・フェローシップによリヨーロッパヘ留学 1963 第48回院展の「建立金剛心図」で奨励賞 (白寿賞・G賞)受賞 1964 日本美術院同人に推挙 第49回院展の「仏説長阿含経巻五」「続深海曼茶羅」 で文部大臣賞受賞 東京芸術大学美術学部日本画科講師となる 1966 東京芸術大学中世オリエント遺跡学術調査団に 参加しトルコヘ イヒララ渓谷の中世キリスト教寺院、修道院の 壁画模写に従事 1967 法隆寺金堂壁画再現事業に携わる 1968 中央アジアを旅行、仏教伝来の源流を訪ねる この旅行がシルクロードに情熱を傾ける発端となる 1969 東京芸術大学助教授となる 1970 日本美術院評議員に推挙 1973 東京芸術大学教授となる 高松塚古墳壁画の現状模写に従事 東京芸術大学イタリア初期ルネッサンス壁画調査団に参加 1975 日本美術家代表団の一員として初めて訪中 1976 第8回日本芸術大賞を受賞 中近東にて平山郁夫日本画展開催 (イラン・イラク・シリア・エジプト・トルコ) 1977 第11回仏教伝道文化賞を受賞する 1978 第63回院展「画禅院青邨先生還浄図」で内閣 総理大臣賞受賞 1979 アテネ・北京・広州にて平山郁夫日本画展開催 中国スケッチ旅行で初めて敦煌を訪れる 1981 日本美術院理事となる 1983 第1回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1984 外務省日本中国文化促進代表団に参加 1985 北京中央工芸美術学院外国人名誉教授となる 第2回東京芸術大学敦煌学術調査隊に参加 1987 第3回東京芸術大学敦煌学術調査団に団長と して参加 1988 東京芸術大学美術学部部長となる ユネスコ親善大使に任命される 文化財保護振興財団が発足理事に就任 1989 日本楼蘭学術文化訪問団団長で楼蘭遺跡訪問 東京芸術大学第6代学長となる 1990 ポロブドゥール遺跡と海のシルクロード取材 のため、インドネシアヘ 1991 「平山郁夫シルクロード展」開催 (フランス国立ギメ東洋美術館) フランス政府よりコマンドール勲章を授与される 1992 日中友好協会会長となる 早稲田大学名誉博士となる 1993 アンコール遺跡救済特別企画「平山郁夫の眼と 仕事」を開催 1994 黒部峡谷を取材 宇奈月町制施行40周年記念特別講演を行う 1995 第13回東美特別展に「幻の瀧」を始めとする 黒部峡谷取材作品を出品 東京芸術大学学長を満期退任する 1996 フランスよりレジオンドヌール勲章を授与される 日本美術院理事長に就任 1998 文化勲章を授与される 2000 奈良、薬師寺玄奘三蔵院「大唐西域壁画」完成 2001 東京芸術大学学長に再任される 日本美術院理事長 東京芸術大学学長 2005 東京芸術大学学長を退任 2009 12月2日死去 享年79歳 平山郁夫は、生涯を通じて150回以上も世界各地の 遺跡を訪問し取材や保護活動を展開してきましたその 中心となったのがシルクロードであり、仏教伝来の道 でした 東京藝術大学で教鞭をとり、作画に励む一方、ユネスコ 親善大使日本中国友好協会会長、日本美術院理事長、 日本育英会会長、芸術研究振興財団・文化財保護振興 財団各理事長などの要職を歴任しながら、公私にわた って展開した文化財保護活動は多岐にわたっています 主な事業だけでも、シルクロード周辺地域を中心とす る文化財・文化遺産の保護はもとより、美術工芸品や 建造物の保存修復に対する助成、伝統技術保持者等の 人材養成事業、芸術研究・文化財保存研究の奨励、海 外主要美術館が所蔵する日本古美術の修復援助、自然 災害や紛争による被災文化財の救出、そして芸術文化 振興への支援等枚挙に暇がありません それらの中でも、ユネスコ親善大使の時に実現した北朝鮮 高句麗古墳群の世界遺産登録をはじめ、アンコール遺 跡や敦煌石窟の保護活動、南京城壁の修復事業などに 対する助成活動、また、なお記憶に新しいバーミヤン 大仏の保護活動等は国際間の友好親善と平和運動に多 大な貢献をなし、世界的にもきわめて高い評価を受け ています こうした偉大な業績により、1998に文化勲章を授与さ れたほか、中国、韓国、フィリピン、パキスタン、ア メリカ、フランス、バチカンなどの諸外国に於いても 数々の賞や勲章を受賞しています平山郁夫 シリア砂漠の夕(シルクロード古都幻想)みずからの被爆体験を原点とした平和への強い祈りは、 生涯のテーマとなる。仏教の源流を遡る旅となり、それ は仏教を主題にした幻想的な作風となり、シルクロード シリーズなどの連作で日本画壇に清新の境地を開拓した
139320 円 (税込 / 送料込)
